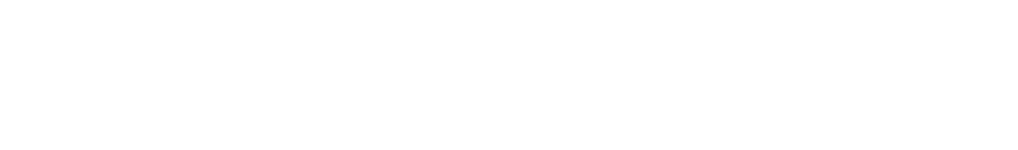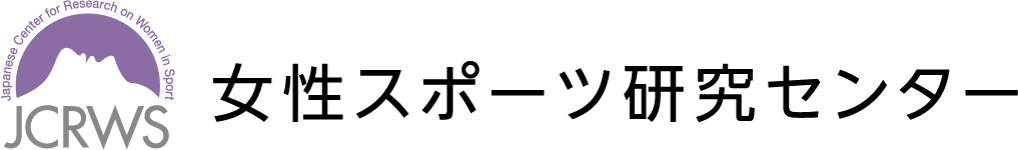Japanese Center for Research on Women in Sport
Japanese Center for Research on Women in Sport
News

- お知らせ
- 2024.04.10
一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ(Wリーグ)と研究協力における包括協定を締結

- お知らせ
- 2024.03.26
「第26回秩父宮記念スポーツ医・科学賞 奨励賞」受賞のご報告

- お知らせ
- 2024.02.29
中高部活女子のための「Girls in Sport」ページを公開しました

- お知らせ
- 2024.01.18
女性スポーツ研究センターが「第26回秩父宮記念スポーツ医・科学賞」奨励賞を受賞することが決定しました

- イベント
- 2023.12.26
「女性スポーツ研究センター 令和5年度研究報告会」を2月3日(土)に開催 ※参加申込は締め切りました(2024.1.31 17:00)

About
We are JCRWS
女性スポーツ研究センターでは、順天堂大学が誇る大学院医学研究科およびスポーツ健康科学研究科のコラボレーションによる研究体制が実現。「研究」という視点から、女性アスリートの支援および女性スポーツの環境改善を目指します。