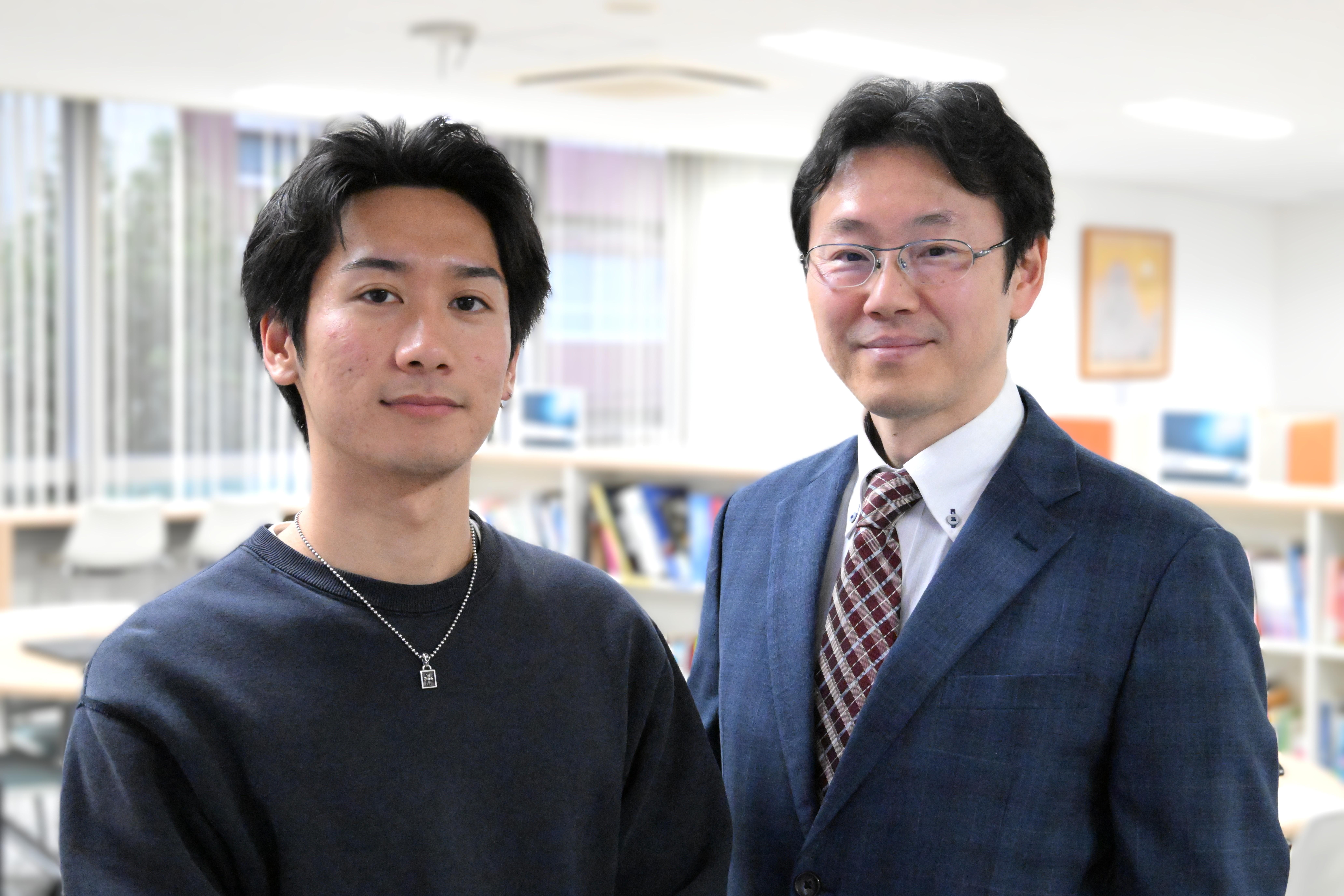学生生活・キャリア Juntendo Scope
- 国際教養学部
- 在学生
オーストラリア留学で見えた自分らしさ
国際教養学部
鷹野 晃成 さん 原和也ゼミナール
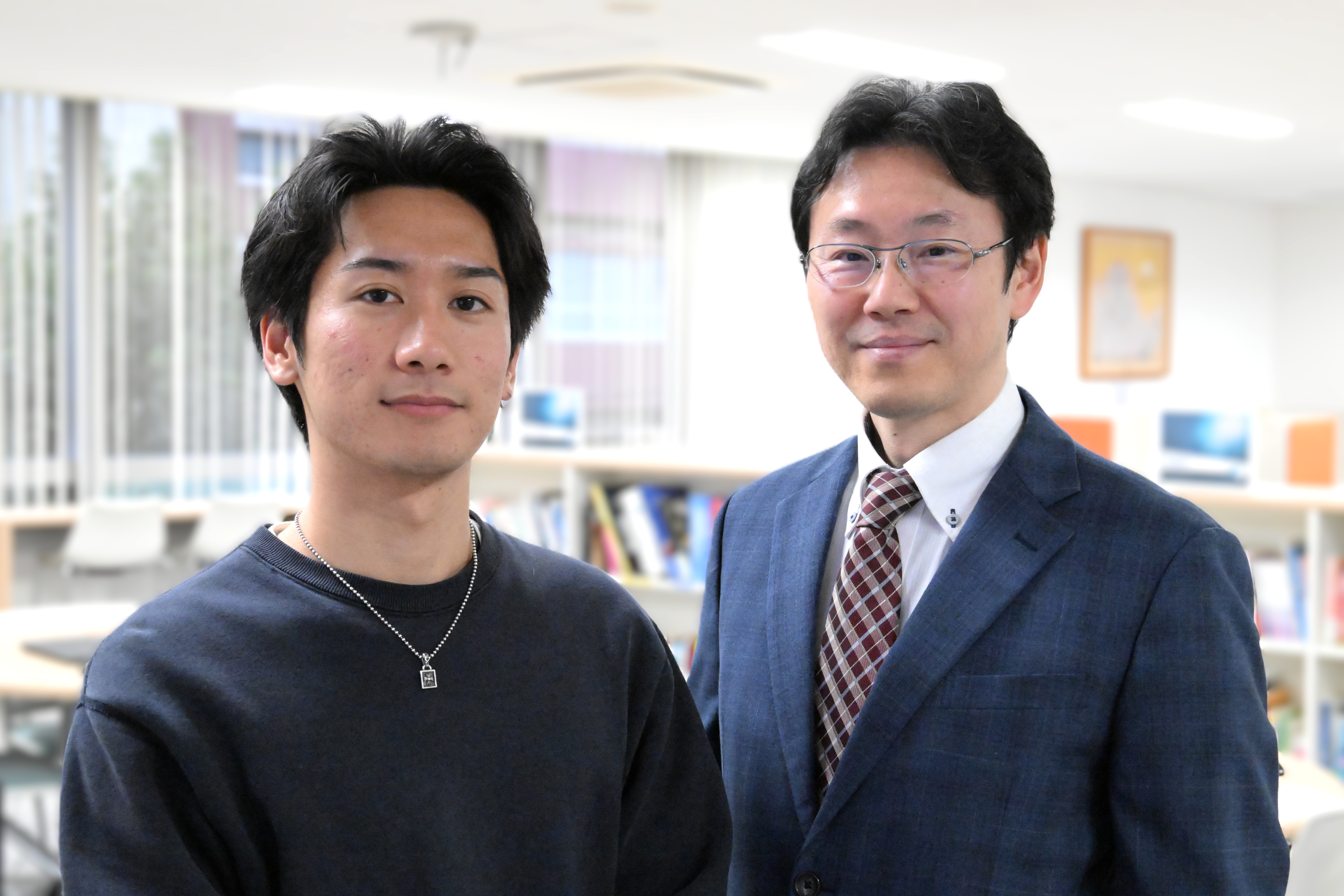
国際教養学部でも留学や海外研修プログラムを多く開講していますが、今回はオーストラリアのAustralian Catholic University(以下、ACU)に10か月間留学をした鷹野晃成さん(4年生)に、ゼミナール担当教員である原和也准教授がお話を伺いました。
『異文化コミュニケーションっておもしろそう!』入ってからも関心が高まった
原和也准教授(以下、原) 国際教養学部はどのような選抜方式で受験しましたか?
鷹野晃成さん(以下、鷹野) 学校推薦の公募型で英語試験と面接試験で受験しました。
原 何か対策はしていましたか?もしくはどのような対策をしましたか?
鷹野 英作文(エッセイ)については高校の英語の先生に過去問を中心に対策してもらいました。面接対策としてはサッカーをやっていたのでその活動を通して学んだことや、時事的なことも話せるように、ニュースを毎日見るようにしていました。
原 通われていた高校はどのような学校でしたか。
鷹野 国際科とかは特になかったのですが、進学校と言われている高校でした。自分は部活動に力をいれていましたね(笑)その中でも英語の授業は好きで、ネイティブの先生もALTとしていて、担当の先生も幼少期から海外在住経験がある先生だったので、発音もしっかり学べる環境でした。
原 英語が好きだったということですが、数ある国際系学部からなぜ国際教養学部を目指したのですか?
鷹野 当時、文理問わずいろいろなことに好奇心を持っていて、特に英語や健康(スポーツ)について学びたいと思い、それがすべてまとまっていたのが順天堂大学の国際教養学部でした。
原 入ってからやってみたいことや興味を持ったものはありましたか?
鷹野 異文化コミュニケーションの領域は入試段階から気になっていました。他の領域ももちろん魅力的で迷ったのですが、パンフレットに書いてある科目や先輩の話をみて、異文化コミュニケーションを学んでみようと思いました。
原 具体的にどのような点に興味を持ちましたか?
鷹野 海外だけではなく、国内でも文化や価値観が違うと感じていたため、そのようなことを詳しく学んでみたいなと思っていました。中でも原先生の講義で、文化のアイスバーグ・モデルについて学んだ時、このような面白い視点があるんだ!と関心し、強く進学を考えましたね。
原 アイスバーグ・モデルでは、皆さんが見えているのは「氷山の一角』の部分であって、水面下の見えない部分に様々な価値観や世界観が存在するということで、ある意味分かりやすいモデルですよね。

原和也准教授
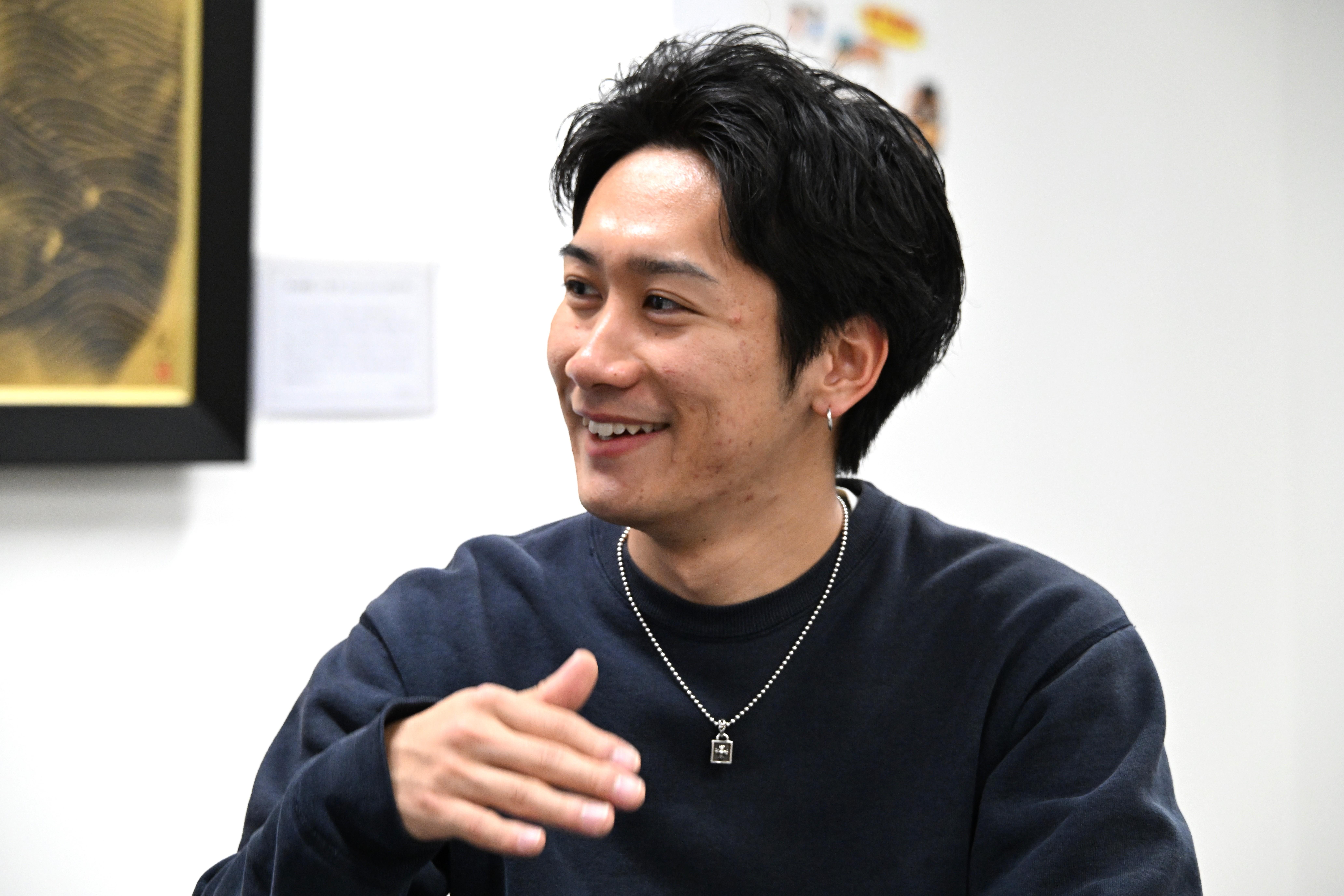
鷹野晃成さん
原 もう4年生ですが、大学生活で、どのようなことが楽しかったですか?
鷹野 英語の授業は本当に面白かったですね。自分の場合はネイティブ・スピーカーの先生が担当する授業が多く、高校では学べなかった内容がたくさんありました。
原 英語“で”学べたのはよいことですね。
鷹野 また、1年目はコロナ時代で制限もありましたが、2年生からその制限もなくなったので、授業やプライベートでも交流が増えて面白かったですね。
原 大学入学後、大変だったことや苦労したことはありますか?
鷹野 論文課題が増えたことですかね。高校までは出されたものをこなすだけでしたが、IBC構造*をしっかり理解した上で自分の考えを文章にしなければならないので、そこのギャップに最初は苦労しました。
原 確かに、答えがないのは大学ならではですね。どのように問題解決したのでしょう?
鷹野 友達と交換して、お互いの添削をしあっていましたね。自分が気づけなかった部分を知ることや、自分の癖みたいな部分も知ることができました。卒論もゼミ生と意見交換をして協力して取り組むことができているので、その習慣が下の学年からつけられてよかったなと思います。
原 とても良い習慣ですし、大切な関係ですね。ほかに国際教養学部での学生生活で印象に残った出来事はありますか?
鷹野 1・2年生の英語の授業はやはり印象的でしたね。とにかく授業内で話す機会が多く、高校までの「文法等をミスしない」「テスト対策」ということではなく、「とにかく英語を話すこと」にフォーカスして、目線やテンポなども知ることができたので、価値観が大きく変わりました。
原 英語だけでも大きく変わることができるのは魅力的ですよね。授業以外では何かありますか?
鷹野 アルバイトなどで色々なコミュニティに属することで、色々な価値観に触れることはとても貴重な経験でした。高校生までの価値観から考えの幅を大きく急速に広げることができましたね。
*IBC構造…文章構成における構造。
I (Introduction) = 導入 ⇒ 何について書くか示す
B (Body) = 本文 ⇒ 理由や具体例を説明する
C (Conclusion) = 結論 ⇒ 主張をまとめる
文化の違いや新たな発見も「パズル」のように繋げ、自分の知識の幅を広げられた

原 オーストラリアへ留学をしましたが、留学に行く前に大変だったことはありますか?
鷹野 ビザなどはエージェント経由でやっていただいたので特に苦労はなかったのですが、IELTSを受験して基準点をとらなければならず、そのための英語は大変でしたね。
原 オーストラリアに決めた理由を教えて下さい。
鷹野 アメリカやカナダも候補としてはあがっていて、アメリカに最初は興味を持ったのですが、銃社会ということもあり、私自身が初の海外でしたので、エージェントからの勧めもあり、オーストラリアに決めました。
原 現地で通う大学はどのように決めたのですか?
鷹野 エージェントが提携しているオーストラリアでの大学が3校ほどで、行きたい大学もあったのですが、自分の語学力や順天堂大学国際教養学部と親和性が高い大学ということもあり、ACUに決めました。
原 親和性が高いことはとても大切ですね。滞在期間中、学生寮ではなくてホームステイにした理由はありますか?
鷹野 ホームステイしか紹介ができないということもあったのですが、どちらか選べたとしてもホームステイを選んでいたと思います。もちろん安全面もありますが、「コミュニティに入れる」ということが大きかったです。コミュニティに入れば半強制的に英語で会話しなければなりませんし、実際に共同作業の機会も多く、必然的にそこでもコミュニケーションが増え、自然と英語が上達できる環境という面が魅力的ですし、私にとって貴重な経験となりました。また、寮だと日本人と同じ部屋になる可能性もあり、自分が留学した目的を果たすためにも、ホームステイで良かったなと思います。
原 語学を学びに行くうえでチャンスが多いことに越したことはないですもんね!現地のキャンパスは広かったですか?
鷹野 僕が行ったACUは国際教養学部と同様で、大きなビル2つがキャンパスだったので、比較的近い環境で学ぶことができました。

Australian Catholic University

大学までの通学路は海外ならではの雰囲気
原 国際教養学部も教育棟2つですし、限りなく親和性が高いんですね!ホームシックやカルチャーショックはありましたか?
鷹野 日本との違いを見つけた時に面白いと思っていたので、特に寂しさとかはなかったですね。発見したことをパズルのピースをつなげていくように、少しずつ広げる感じでしたので、楽しさの方が多かったですね。
原 実際にオーストラリアに行ってみて、日本との違いをどのようなところに感じましたか?
鷹野 日本は思ったことをあまり言わない文化だなと感じました。誉め言葉であっても日本では「嫌味に聞こえてしまうかもしれない」と気が引ける部分もあると思いますが、海外はどんどん思ったことを口にしていくので、日本も取り入れられる部分があるといいなと思いました。
原 日本はお互いに「察することが第一」の文化ですが、英語圏ですと、バレーボールのラリーのように、言葉が飛び交いますよね。
鷹野 自分自身、海外スタイルの方がストレスもなく好きだなとも気づけましたね。
原 日本に帰ってきて、逆カルチャーショックみたいなものはありますか?
鷹野 満員電車ですね(笑)あとは握手やハグが少ないので少し距離感に寂しさはありました。
原 挨拶もフレンドリーですもんね。現地では日本のコンテンツや日本語に触れる時間というのはありましたか?
鷹野 ほとんどなかったですね。英語能力を伸ばしたかったのもあるので、ゼミ以外では極力日本語に触れないようにしていました。
原 いわゆる「オーストラリア英語」はどうでしたか?
鷹野 最初は戸惑いましたが、2~3カ月すれば耳も慣れましたし、ほとんど違和感はなくなりました。途中、ホストファミリーから「オーストラリア人っぽくなったね」と言われた時は嬉しかったですね!
原 認められたときの鷹野くんの笑顔が想像できます!ちなみに、スペリングはブリティッシュ式なのですか?
鷹野 そうですね。PCもオーストラリア用で設定変更をしていて、論文課題提出の際に注意書きが出てくるのも最初は新鮮でした。

大量の野生カンガルーが裏庭にいる環境もAUSならでは

気軽に遊べるのもホームステイのいいところ
国際教養学部の基礎演習や英語の授業は留学先で活きてくる!
原 現地での学びはいかがでしたか?
鷹野 最初のうちはオンラインもあったので少し緊張しましたし、温度差を感じる難しさはありました。ただ、所属しているゼミナールが異文化コミュニケーションでしたので、現地で学ぶことや感じたことが実際に文献に載っていたりしたので、そういう意味では自分ごととして落とし込むことができてよかったと思います。
原 「現地の大学ならでは」と感じた授業などあれば教えてください。
鷹野 ライフデザイン系の授業を多くとっていたのですが、自分で決めた街や地域を実際に3-4時間訪れ、そこで感じたことをまとめたものを発表する授業がありました。課外活動系の授業は順天堂でもありますが、より多く取り入れても面白いのではないかなと思いました。
原 感じたり気づいたりすることで終わってしまうのは勿体ないと思うので、インスピレーションを言語化して発表するのは面白いですよね。
鷹野 発表や討論も、先生が止めるくらい学生がどんどん積極的に発言していたのも刺激的でしたね。
原 他のアジア系の留学生はどうでしたか?
鷹野 やはり遅れていたような部分はありました。ネイティブのスピード感でどんどん展開されていくので、専門用語の英訳がわからないと入りづらさはありましたね。もちろん積極的に意見するようにはしていましたが、ニュアンスがわかっているのに出てこないもどかしさも多く感じました。
原 日本人は、英文法を学び、ライティングもしっかりと学んでいると思うのですが、聞く・話すの技能面はどうでしたか?
鷹野 私自身がライティングよりもリスニングやリーディングの方が得意だったこともあったので、直接的に感じることはなかったですが、現地で知り合った日本人の学生はライティング能力の方が高いことが悩みでもあったので、お互いで悩みや質問をシェアすることはしていました。
原 逆に「現地の授業よりも国際教養学部の授業の方がいい!」と思ったものはありますか?
鷹野 1・2年生次の英語ですね。最初の20週間で受けていた授業が、国際教養学部の英語のスタイルや教えと一緒のものが多かったので、本当に充実した授業を受けていたのだなと確認することができました。
原 基礎演習(リベラルアーツ演習)で学んだことは役に立ちましたか?
鷹野 役に立ちました。授業で聞いた内容を分からない内容をまとめて授業理解をしていたのですが、基礎演習で得たインプットとアウトプットの流れが活きました。引用の悪例なども「当たり前」とすぐに理解することもでき、本当に重要なことを勉強していたんだなと再認できましたし、国際教養学部はいい授業ばかりだなと多く思えました。
原 留学中にオンラインでゼミナールに参加していて、週1回だけ日本語に触れる形になりましたが、その部分はいかがでした?
鷹野 日本語が出づらくなったのはありましたね(笑)日本語の単語や言い回しが出てこなかったりしたので、それが少し新鮮で貴重な体験になりました。
原 プチ失語症みたいな感じですね(笑)
鷹野 英語だと主語と動詞が先に来るので、比較的内容が序盤に理解ができるのですが、日本語だと後の方に動詞や大切な部分がくるので、解釈が若干しづらくなった部分があったのは新鮮で面白かったです。
原 遠隔でゼミ長も務めてくれましたよね!正しい日本語でしっかりコミュニケーションとれていましたよ。
鷹野 そこはしっかり生まれ育ったものが身に染みていましたね(笑)
原 辛かったのは、ゼミの終わりに皆と食事やラーメン屋に行けなかったことくらいですか?
鷹野 唯一のstruggleでした!!(笑)
原 英語を駆使する日々だったと思いますが、日本語の方が楽だなと思うことはありますか?
鷹野 テレビをつけていて、スマホやPCを開きながらも内容が聞き取れるのが楽だなと思います。向こうにいた時、特に最初の頃は、常にニュースならニュース、動画なら動画に集中していないといけませんでしたが、やはり慣れ親しんだ母語は何も気にしなくて良いということはありますね。ただ、帰ってきてから日本語ばかり聞いていると「英語の感覚が鈍ってしまう!」と思うので、今でも定期的に現地のニュースを見るなど、しっかり英語を聞くようにもしています。
原 そんな中、留学から帰ってくる直前期はどのような気持ちでしたか?
鷹野 ホストファミリーが本当に素敵な家族で、初日から本当の家族のように接してくれたので、「帰りたくないな」という思いはありましたね。ただ、日本にいる友達や仲間とまた会える楽しみもあったので、毎日帰りたいと帰りたくないが揺れ動くアンビバレントな感じでしたね。
原 それは素敵ですね!今でも心はどこかオーストラリアにあるんでしょうね!

ホストファミリーとその親族と一緒にクリスマスパーティーを楽しむ
留学もチャレンジも今しかできないことを積極的に!
原 今後のビジョンをお聞かせください。
鷹野 英語を必ず使う仕事に就きたいとは今は考えておらず、コミュニケーションツールとして自分でストックしたいと思っています。就活も幅広い業界で行っていますが、自分が何かしたいと思ったときにチャレンジできるようにはしたいです。
原 オーストラリアで働きたいとは思いますか?
鷹野 やはりオーストラリアの方が私の感覚に合ったコミュニケーションや暮らしがありましたので、訪れたいなと思うことは多々あります。ただ、すぐにオーストラリアで働くビジョンはそこまで強くはなく、留学で得た多くのコネクションを自分の幅として捉え、将来的に海外で挑戦ができたらいいなと思っています。
原 色々な経験をしてきたと思いますが、最後に後輩や高校生に向けてアドバイスをお願いします。
鷹野 社会人になったらやりたいこともやれなくなると思うので、どんどんやりたいことにチャレンジしてもらいたいと思います。僕も1・2年生での学びがあったからこそ、留学に行って前向きに色々な経験ができましたし、是非、順天堂大学の国際教養学部に入り、多くのことを学び、たくさんのことに挑戦してもらえたら嬉しいです。