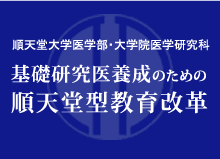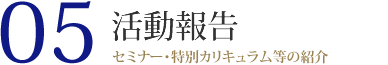2025.01.10
第11回新潟大学・順天堂大学連携セミナーを開催しました
基礎研究医養成プログラムでは、研究医養成において連携している新潟大学と合同で、両大学の基礎研究医を目指す学生向けのセミナーを行っています。
今年度は、2025年1月10日(土)14:20から、学生研究発表会に続きZoomによるWebセミナー形式で、第11回新潟大学・順天堂大学連携セミナーを開催しました。
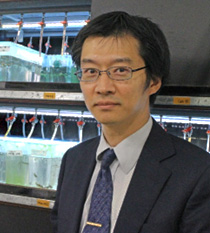
講演者 松井秀彰 先⽣
特別講演①は、新潟大学学生運営代表・医学部5年生の佐々木祥乃さんの司会により、新潟大学脳研究所 脳病態解析分野 教授 松井秀彰先生にご講演いただきました。
「様々な生命と考える神経難病の病態」をテーマに、はじめに松井先生の研究者となるまでの歩みやこれまでの研究歴についてお話しいただきました。続いて、パーキンソン病やアルツハイマー病などの病態解析に関する研究について、老化反応とアルツハイマー病の病態の違いを対比しながら解説されました。また、進化の過程において「早熟と長寿は両立しない」という視点から、魚モデルを用いた疾患研究についても興味深いお話しがありました。さらに、脳研究所における研究と臨床解析の関係性や、臨床応用の可能性についても詳しくご説明いただきました。
参加学生からは、先生がどのようにして研究の道を選ばれたのか、研究内容だけではなく、ご経歴や研究に対する向き合い方を詳細にお話いただける機会は非常に貴重でした、ヒト以外の生物を用いた研究の面白さを感じました、など、松井先生の研究者となるまでの経緯、研究に対する熱意を通して、多くの方の研究への興味が刺激されたようです。

講演者 加藤忠史 先⽣
特別講演②は、本学学生運営代表・医学部5年生の劉行さんの司会により、順天堂大学医学部 精神医学講座 教授 加藤忠史 先生にご講演いただきました。
「双極性障害の謎に挑む ― 研究者としての道のり」をテーマに、双極性障害の発症や進展がゲノム異常と関係していることを踏まえ、その原因解明と治療法の開発に向けた研究について詳しくお話しいただきました。また、ご自身の学生時代の経験や、精神科を選んだ理由、さらには双極性障害の研究に取り組むことになった経緯についてもお話しいただきました。
最後に、これから研究を志す学生に向けて、「臨床の中に疑問を見つけること」「研究を進める環境の強みを理解すること」「活用できる技術を使うこと」「まずは挑戦してみること」といった、日常の中で研究のヒントを見つける重要性について励ましのメッセージを送ってくださいました。
参加学生からは、先生が臨床、研究、臨床と行き来され、その経過が必要と感じられている事が印象的でした、ご講演の中で特に、臨床研究と基礎研究の目的、方法、解析、発表の違いについてのまとめが非常に勉強になりました、先生の研究テーマの変遷をうかがうことができる貴重な機会となり、勉強になるとともに勇気づけられました、など感想をいただき、これから基礎研究、臨床研究のいずれを目指す方にも大いに励ましになったようです。