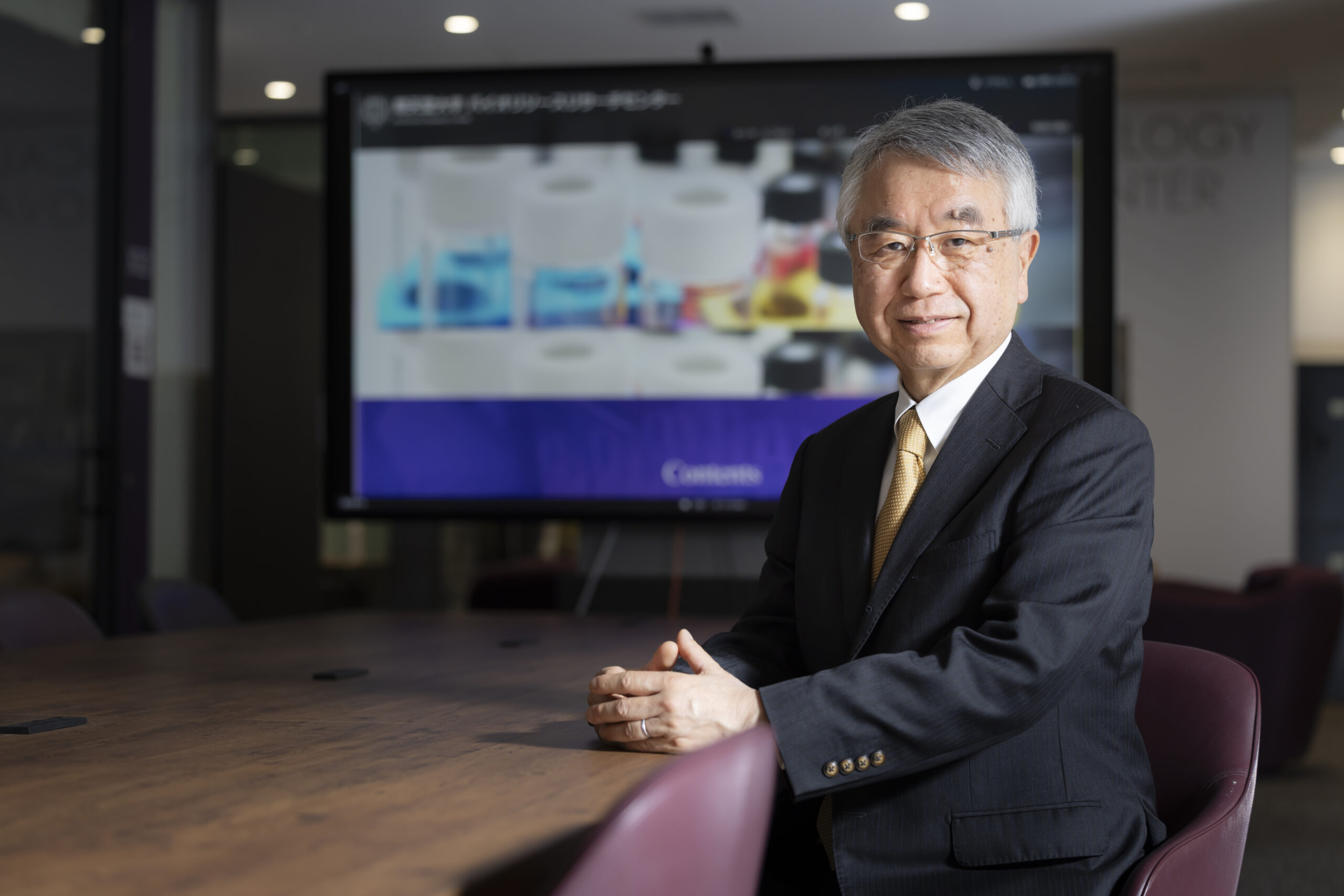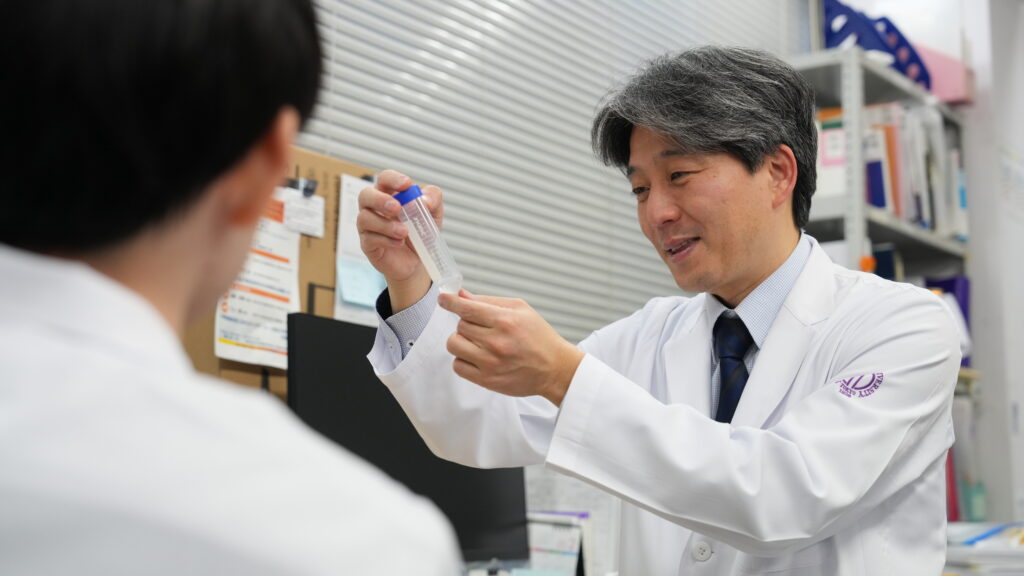バイオリソースリサーチセンターは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者や健診を受診した職員の検体のほか、消化器外科の残余検体などの生体試料を収集し、匿名化した臨床情報とひも付けて保管しています。生体試料とデジタル情報によるバイオバンク事業を通じて研究を支援する本センターの取り組みについて、高橋和久センター長に聞きました。
COVID-19の検体収集をきっかけにバイオバンク事業を展開
バイオリソースセンターが設立されたのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによって病院に集まった多くの検体(血清、ウイルス検体、細菌の分離株)を研究に活かそうと考えたことがきっかけでした。そこで、2021年10月、COVID-19患者や健診を受診した職員の検体を収集・管理する目的で産学協同研究講座「バイオリソースバンク活用研究支援講座」が開設され、2023年末までに職員健診の15,259 検体、COVID-19の25,176 検体、細菌分離株の23,312 株が保管されました。
その事業を引き継ぎ、2023年10月にバイオリソースセンターが開設されました。本センターではCOVID-19と職員検体に加えて、消化器外科が保管してきた手術の残余検体を保管し、より多くの診療科や講座の研究者が利活用できる体制を整えようとしています。今後は、婦人科、乳腺科、呼吸器外科、耳鼻咽喉科などで扱う固形がんの検体についても一括管理する予定です。
センターにはそれらの収集や基盤整備、リソース管理を行うために以下の4つの研究室を設置し、それぞれの分野のスペシャリストが研究室代表を務めています。
①生体試料のバイオバンキング事業を行う「バイオリソース先端研究室」
②バンキング検体と臨床情報を結合したデータベースを構築する「生体情報システム化研究室」
③臨床検体を用いてバイオマーカー開発やゲノム研究を行う「遺伝子解析モデル研究室」
④本学医療データの一元管理を行うためのインフラ整備を行う「医療情報利活用推進室」

順天堂大学の9学部6病院の情報連携・共同研究をサポート
バイオリソースリサーチセンターは、順天堂大学の学術研究の推進施設と位置づけられています。バイオリソースの利活用については、研究開発へのバンク資源の活用・分譲(研究者の要望に応じたオンデマンド型バンキングを含む)がスムーズに行えるよう支援するほか、研究者と診療科の共同研究、センター内研究室との共同研究を推進します。
センター設立1年目は、臨床検査部、病理診断センター、情報センターとともに残余検体保存システムを構築し、提供者の文書同意を得た上で保存を開始しました。2024年10月からの4年間は、厳密な情報管理システムのもとで、順天堂大学医学部附属の6病院間や9学部間での横断的な利用が可能な検体バンクとデータベースのフレームの制定を目指します。将来的には、浦安病院や静岡病院の検体を収集し、臨床情報とともに一括管理できる体制を構築していきます。
また、診療業務などで多忙な臨床医や、本郷・お茶の水キャンパスから離れた病院や学部に在籍している研究者の研究活動を後押しし、診療科や学部を超えた研究成果の創出にも貢献していきます。中でも特に期待を寄せているのは、設立間もない薬学部との連携です。2026年4月に設立予定の大学院薬学研究科を中心とした創薬研究などで、本センターのリソースを役立ててほしいと考えています。
ティッシュバンクは生体試料の「タイムマシン」
順天堂大学医学部附属順天堂医院の手術件数は、年間1万7000件と、日本トップクラスの数を誇ります。そのうちの消化器外科の約800件分の残余検体を収集・保管して、再利用できるように、消化器外科では数年前から「ティッシュ(細胞組織)バンク」を整備してきました。この取り組みを消化器外科内にとどめるのではなく、より広く活用しようと、本センターのバイオリソース先端研究所と統合したバイオバンク事業が始まりました。

遺伝子解析モデル研究室 奥澤淳司室長
消化器外科が保管している残余検体は、消化器がんのがん組織と正常組織をそれぞれ10ミリ立方サイズに切り出したものと血液検体です。その3種類をワンセットで保管することを、私は「タイムマシン」と呼んでいます。検査・診断技術の進歩は極めて早く、今は調べられないことが数年後には調べられようになるかもしれません。そのような技術が登場したときに高精度で調べることができるように、新鮮な状態のまま保存可能な-80℃のディープフリーザーで保管しているのです。
遺伝子解析モデル研究室はセンター内のほかの3つの研究室とは異なり、臨床検体やそれらと紐付けられた臨床情報を用いた研究を行う研究室です。最新の次世代シーケンサーなどで臨床検体を解析し、バイオマーカーの開発やゲノム研究を展開します。

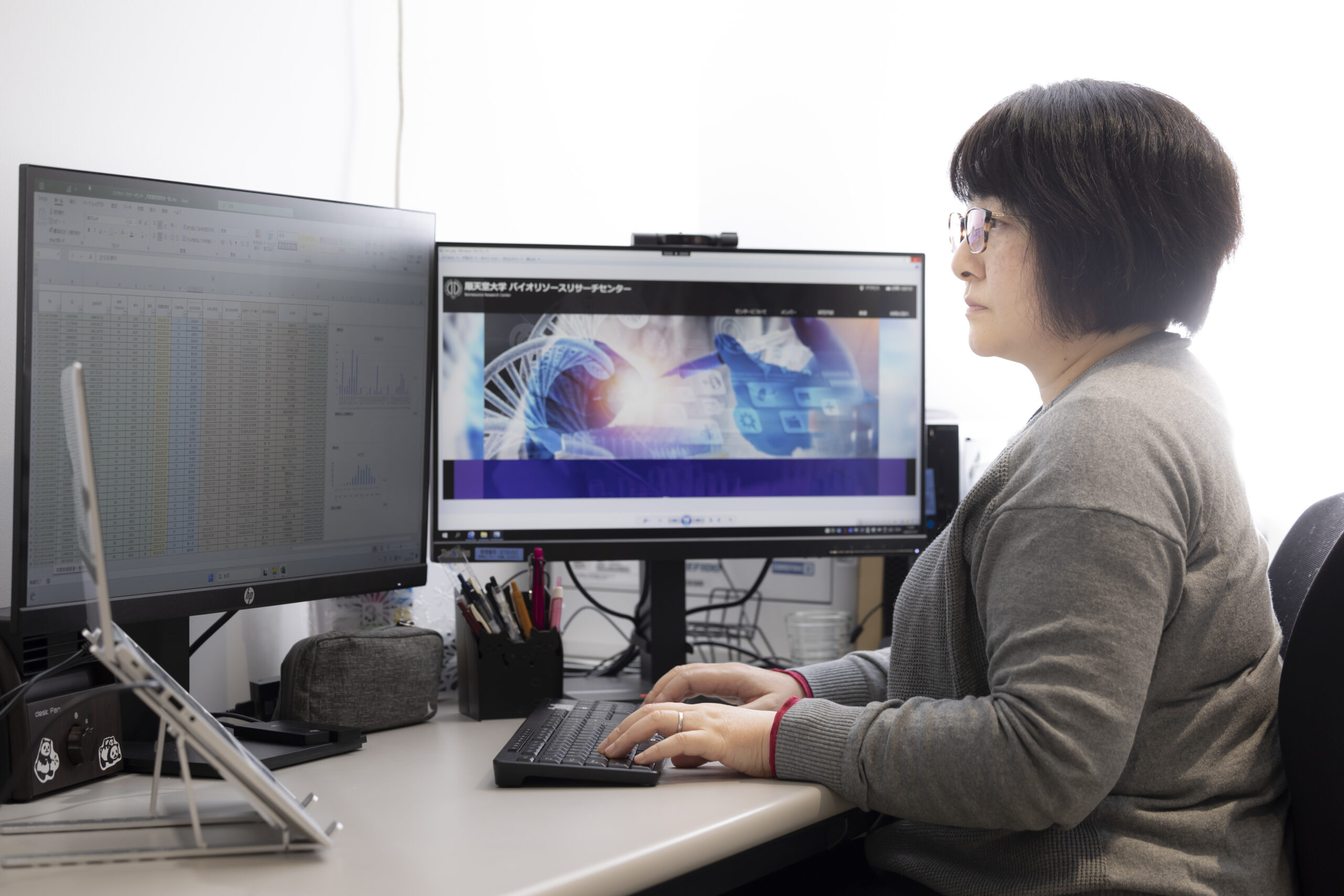
臨床検体を用いて疾患関連遺伝子の機能や発症メカニズムを解析
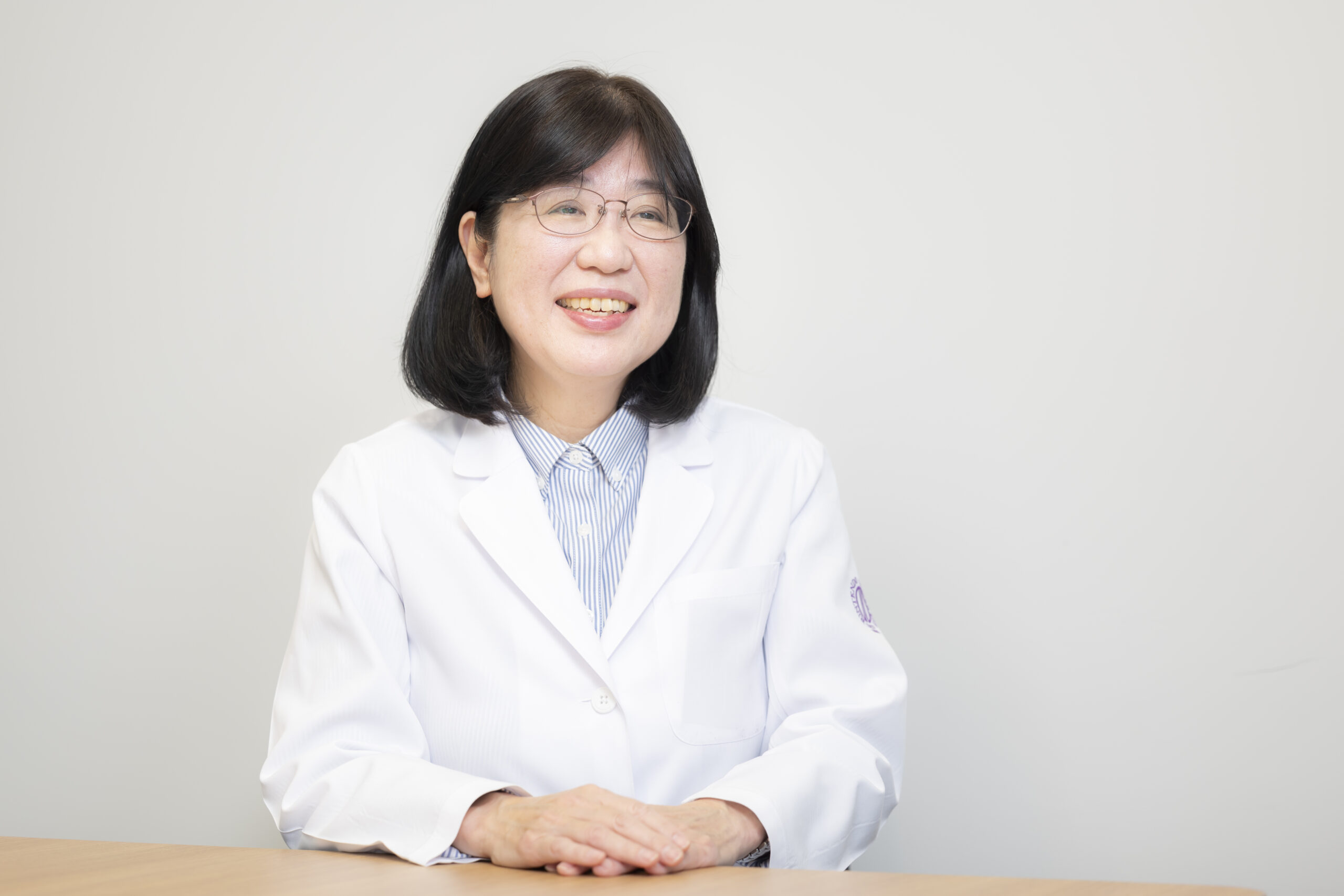
バイオリソース先端研究室 田部陽子室長
順天堂大学学内で血液などの臨床検体を使った研究を行う場合、研究室や診療科からの要請を受け、順天堂医院の臨床検査部が検査残余検体の一時保管などのサポート業務を担っています。一方、手術の残余検体については、多くの外科系診療科がそれぞれ個別に保存作業を行ってきました。こうした状況の中、システマティックに手術残余検体を保存していた消化器外科のティッシュバンクを引き継ぐ形で、バイオリソース先端研究室のバイオバンク事業が開始されました。
今後さらなる検体の増加を見越し、全学組織として保管スペースを確保するとともに、組織的な運用体制の整備を開始しました。今後は、消化器外科以外のさまざまな診療科の臨床検体を保存する計画です。さらに、病理組織検体を保管する病理診断センターや血清や尿などの検体を保管する臨床検査部との連携も進めています。
また、生体情報システム化研究室では、ドライ医療情報の収集、臨床検体と診療情報との関連付け及びDX化を推進します。
バイオリソースリサーチセンターは、順天堂の全ての診療科、学部、講座の研究活動を支援する基盤組織です。将来的には、学外の組織や企業への利用拡大も視野に入れていますが、まずは順天堂内の研究者や臨床医による利活用を推進していきます。

医療RWDの病院間連携を可能にするインフラ基盤を構築
手術検体などの生体試料の収集と並行して、臨床現場で得られた「医療リアルワールドデータ(RWD)」を利活用するための基盤づくりにも注力しています。RWDの利活用において重要な「How to collect(収集)」「How to use(利用)」「How to manage(管理)」という3つを軸に、データベース構築やインフラ整備を進行中です。
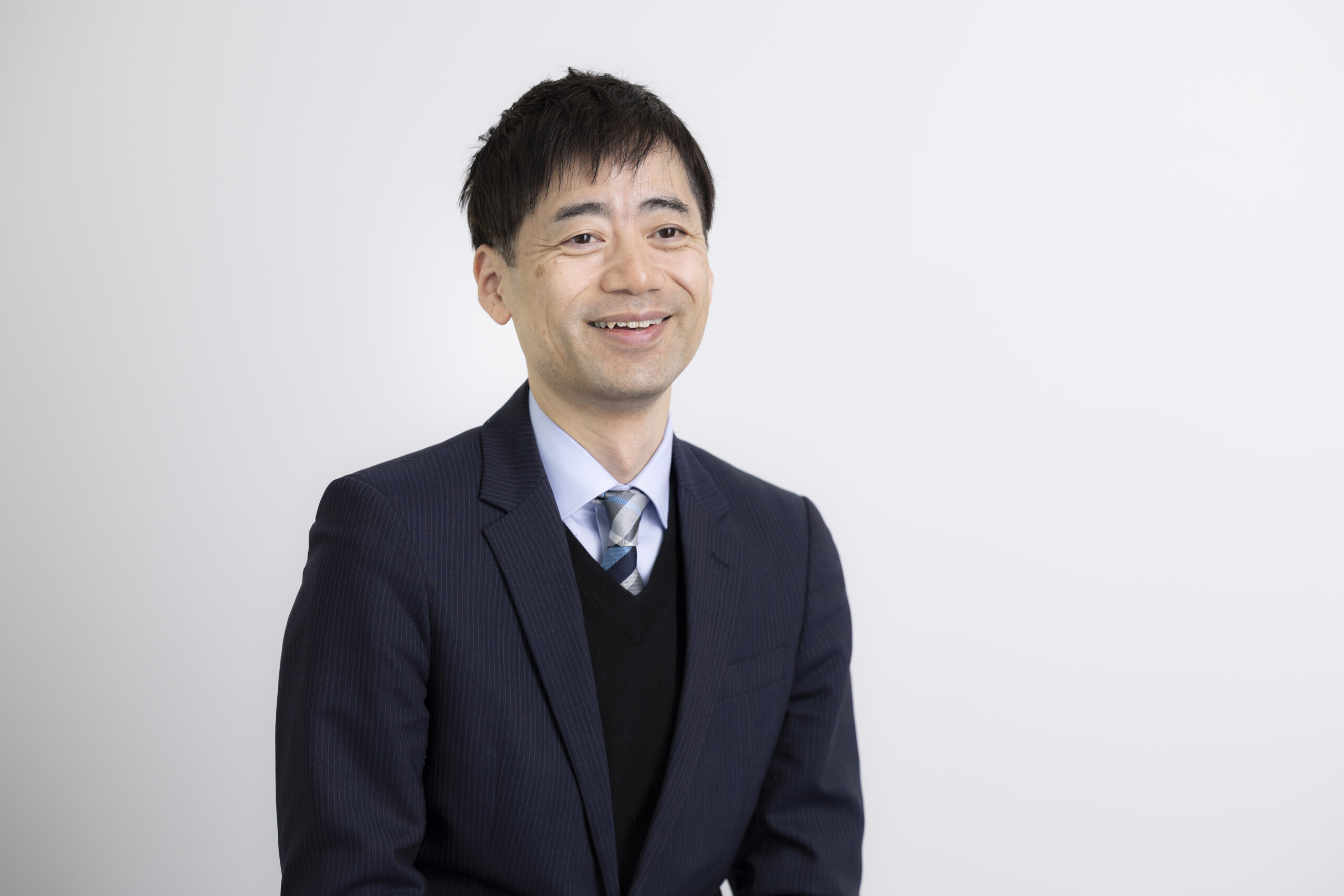
生体情報システム化研究室 内藤俊夫室長
「How to collect(収集)」については、生体情報システム化研究室が中心となってインフラ整備を推進しています。このシステムの通信規格には国際的な標準規格であるHL7FHIRを採用しています。また、附属病院間での情報連携を進めるためにはカルテ情報などを標準化する必要がありますが、現時点では病院によってバラバラなことが多く、正しいコードを付与してマッチングさせる作業も並行して進めていきます。

医療情報利活用推進室 藤林和俊室長
2024年8月に新設された医療情報利活用推進室は、「How to use(利用)」「How to manage(管理)」にあたる役割を担います。2025年度中に次世代医療基盤法に対応することを目標に、診療や研究により蓄積された医療RWDを研究利用および研究外二次利用できるようにする体制整備を進めています。RWDの研究内利用であれば倫理指針に基づいて倫理委員会を通すことができますが、例えば人工知能のアルゴリズム開発のためにRWDを使う場合は研究内利用ではなく研究外二次利用となります。今後学内で社会実装も見据えた人工知能関連の研究開発が増えていくことも考えられることから、次世代医療基盤法と個人情報保護法に対応した管理体制の構築に向けて、準備を進めているところです。

研究者Profile

高橋 和久
Kazuhisa Takahashi
健康総合科学先端研究機構バイオリソースリサーチセンター
センター長
Researchmap