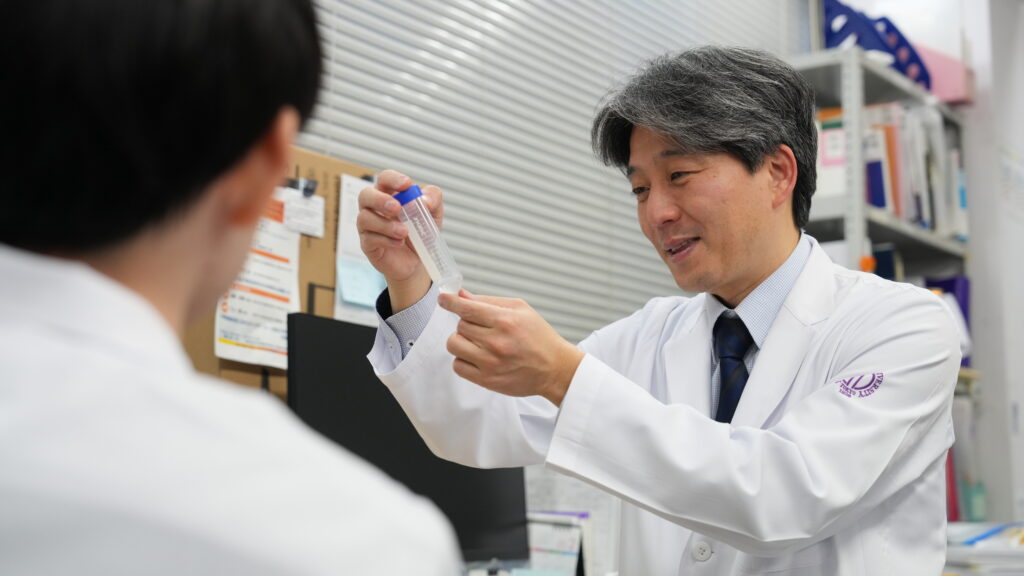シミュレーション教育研究センターは、看護系では国内唯一のシミュレーション教育のための研究施設です。多様なシミュレーション教育を実践しつつ、より良い教育環境を構築し、看護のBest Practiceを目指して研究を進めます。センターが展開するシミュレーション教育研究について、植木純センター長と寺岡三左子副センター長にお聞きしました。
日本のシミュレーション教育の先駆的存在
実際の医療現場を再現できる研究拠点を設立
植木 当センターの研究対象であるシミュレーション教育は、実際の臨床現場を再現した状況で人や物に接しながら医療行為やケアを経験し、専門知識や技術、態度を統合した教育のことで、約20年前からアメリカを中心に発展してきました。日本でも約10年前から広がりつつありますが、その中でも順天堂大学医療看護学部は他大学に先駆けてシミュレーション教育を積極的に導入してきた大学です。
当センターは、さらなる看護のBest Practice(最善の手法)の実現に向けた、シミュレーション教育に関する研究の推進、先端的な教育手法の構築、ICTを活用したシミュレーション教育の展開を目的としています。看護系では国内唯一のシミュレーション教育における研究施設です。センター設立当時はCOVID-19のパンデミックにより病院実習が困難だったため、新興感染症まん延に負けない教育環境を構築するというミッションも担ってきました。
体育館だった建物を利活用して作られた約450㎡のスペースは、使用目的に応じてコンパートメント化できる可変式の28ブースで構成。仕切り位置を変えることでクリティカルケア病棟、小児病棟、周産期センター、手術室、外来、ナースステーション、在宅などの医療現場を再現することが可能で、附属病院で使用しているIBMの電子カルテも15台設置しました。将来的には、各コンパートメントを仕切るロールカーテンに映像を投影するプロジェクションマッピング技術を組み合わせ、さらにリアルな臨床環境を再現したいと考えています。

「わかる」から「できる」へ
学生の主体性を育む教育環境
寺岡 当センターは、シミュレーション機器やICTを活用してリアルに近い臨床環境での学びを提供し、看護実践力を高めることをミッションとする研究施設です。シミュレーション教育のプログラムは、国際基準に基づいて設計しています。単純に臨床現場を再現すれば良いのではなく、どのようなスキルを身につけるのかといった目標を明らかにして、そのための学習要素をシミュレーションするシナリオに盛り込みます。明確な学習目標の設定と目標に応じた教材の活用が重要です。そして、学習する人を中心に考えた、学習者中心のアプローチを行います。
安全が確保された環境の中で生産的な失敗をすることで、どうすれば良かったのか、不足している知識が何なのかを学習者自身が気づき学習を進めることで学びの効果は高まります。経験からの振り返り、自己評価による気づきによって知識と技術の統合が始まると考えますので、それにより「わかる」から「できる」になることを目指します。このような学びの環境における教員の役割は学習者に教え込むというよりは、学習者自身が目標を達成できるように導くファシリテーターだと捉えています。
先に述べたセンターのミッション実現を目指し、シミュレーションによる教育効果に加え、シミュレーションによる学びそのものを研究対象としています。そこからシミュレーション教育のエビデンスを積み上げ、日本の看護学生のために最適化したシミュレーション教育方法を確立することを目指しています。

シミュレーター機器の活用に加えてメタバース空間に臨床環境を構築
植木 当センターは2022年4月に開設され、改修の終了した同年秋に本格稼働が始まりました。現在は新しい研究に着手しながら研究環境を整備する助走期間です。センター内にはポスドクのためのスペースも確保し、2024年度よりポストドクトラルフェローの公募や事務担当職員の配置を始めました。ここから研究活動のさらなる活性化、競争的研究資金の継続した獲得を進めていきます。
研究の柱の1つである「シミュレーター機器を活用した研究」では、成人、高齢者、周産期、小児、新生児の高機能シミュレーター10台を含む17台の患者シミュレーター、蘇生トレーニング用マネキン、基本手技シミュレーターなどを用いて、学生が主体となって学ぶアクティブラーニングを展開。シミュレーション教育手法を検証することで最適化した検証結果を教育現場にフィードバックし、現場での教育効果をさらに研究に生かすという好循環を生み出すことが狙いです。
もう1つの「ICTを導入したシミュレーション教育システムの研究」では、本学医学部のメディカル・メタバース共同研究講座や健康データサイエンス学部と連携するなど、メタバースを導入したシミュレーション教育の開発と効果の検証に取り組みます。例えば、手術室をメタバース空間で再現したシミュレーションを展開できればと考えています。


すべての教員が当センターを活用
個々の研究のレベルアップも目指す
植木 シミュレーション教育を研究対象とする教員だけでなく、すべての分野の教員たちもシミュレーション教育に関心を寄せていることが本学の特徴です。2022年度は10月からの約半年で34コマでしたが、2023年度は医療看護学部の228コマの演習・実習と大学院のシミュレーション看護学に活用されるなど、活用事例も拡大しています。
当センターが展開するシミュレーション教育の対象者は、学生や医療スタッフにとどまらず、術前後や急性・慢性疾患患者へのセルフマネジメント教育にも拡大した研究を展開中です。例えば、「ICTを用いたセルフマネジメント支援」の研究では、スマホやタブレットなどのモバイルアプリを活用した医療サービスを開発しています。
また、AIを搭載したセルフマネジメント支援アプリを開発し、患者さんが自らの呼吸管理や浮腫の評価などを行うシステムを構築するとともに、看護の実践とリンクさせていくことも可能になるでしょう。今までに、COPD(Chronic Obstructive Pulmonary Disease:慢性閉塞性肺疾患)、ぜん息などの呼吸器疾患、慢性心不全、SSI(Surgical Site Infection:手術部位感染)予防、在宅酸素療法など、在宅支援が重要になる疾患や治療を対象としたアプリ開発に取り組んでいます。

高校生への看護体験講座など展開の可能性はさらに広がる
寺岡 教員と学生の双方から高評価を得ているシミュレーション教育ではありますが、本学は日本一の看護系学生数を有するため、すべての学生が効果的なシミュレーション教育を経験することが難しいという課題があります。また、シミュレーション教育は設備のあるキャンパスにいなければ学習できないため、場所や時間を問わずに学習できるeラーニング教材の開発研究も行っています。シミュレーション機器で手足を動かして手技を学び、eラーニングで判断や思考のトレーニングをする。このように学習方法を“ブレンド”することで、臨床現場での実践力を高めることができると考えます。
植木 安全にリアルな臨床現場を経験できるシミュレーション機器を備えた当センターは、非医療者に向けて本学の医療看護学部の強みや看護学の魅力を発信する好機にもなるはずです。具体的には、高校生を対象とした看護体験講座の展開や高大接続への活用、市民公開講座の展開などが考えられます。
また、アジアからの留学生への教育や遠隔シミュレーション教育など、学外および海外の研究者への展開も期待しているところです。シミュレーションホスピタルを持つマイアミ大学など、MOU(基本合意書)を結んでいる海外の大学との共同研究も活発に行い、シミュレーション教育やICT活用の情報発信拠点としても存在感を示していきます。

研究者Profile

植木 純
Jun Ueki
大学院医療看護学研究科シミュレーション教育研究センター
センター長
研究者Profile

寺岡 三左子
MIsako Teraoka
大学院医療看護学研究科シミュレーション教育研究センター
副センター長
Researchmap