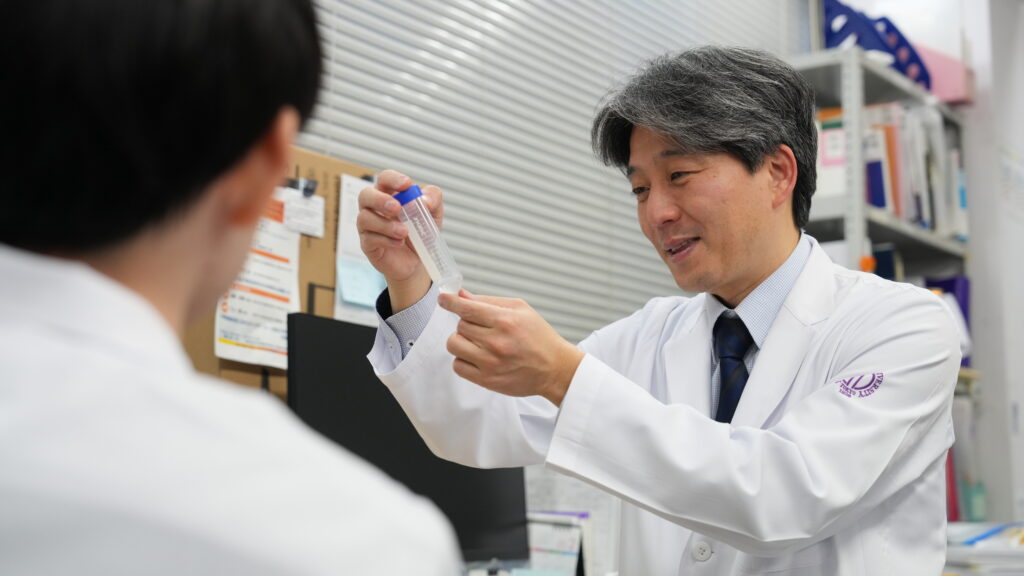加齢や高齢化の諸問題を多面的に研究して健康寿命の延伸に貢献
ジェロントロジー研究センターは、超高齢社会のニーズに対応するウェルビーイングの実現を図るために、分野横断型のプロジェクト拠点として設立されました。加齢や高齢化に関するあらゆる分野の知識を集積し、健康寿命の延伸に貢献することを目指す本センターのプロジェクトについて、内藤久士センター長に聞きました。
アクティブ・エイジングを図るためのジェロントロジー

"ジェロントロジー"は、一般的には「老年学」や「加齢学」などと訳されますが、私たちはよりポジティブに捉えて、高齢になっても社会参加を続けられるアクティブ・エイジングやウェルビーイングを図るための学問と定義しています。その上で、医学とスポーツ・体育に強みを持つ順天堂らしさを活かしつつ、生活行動学、社会包摂・文化・芸術や情報科学・地球科学・生態学、さらに多数の文科系学問分野とともに研究し、人類の福祉に貢献する学問領域を確立しようとしています。
現在は、この考え方を拡張し、各分野の連携をさらに強化するとともに、研究成果の社会実装に向けた産学官連携の取り組みを進めているところです。その基盤として、順天堂大学の9学部6研究科6病院(2025年現在)のリソースを最大限活用するため、部門横断的な研究組織と仕組みを構築することに重点を置いています。
各分野の連携拠点となる本センターは、高齢社会のさまざまな研究課題に対して産学連携で取り組む「ジェロントロジープロジェクト」と、AIやIoTを活用することで健康寿命延伸への貢献を目指す「COI展開プロジェクト」という2つの研究プロジェクトを展開。プロジェクトを通じて企業や地域との連携を強めるとともに、若手研究者の研究力向上にも力を注ぎます。
COI研究を引き継ぐ「ジェロントロジープロジェクト」
ジェロントロジープロジェクトは、本センターの前身である寄付講座「ジェロントロジー:医学・健康学応用講座(代表:佐藤信紘)」が進めてきた文部科学省/JSTのCOI研究を引き継ぐ形でスタートしたプロジェクトです。元となったCOIプロジェクトでは、幸福寿命を延ばす医療イノベーション達成に向けて、ロコモ抑止を目的とするさまざまな研究と実践を行ってきました。青年期からのロコモ未然防止に向けた介入方法の開発にも取り組むなど、高齢期にとどまらない研究が特徴的です。
その流れをくむジェロントロジープロジェクトは、生涯を通じた成長・加齢という視点で老化を捉え、人々が最後まで自分の足で動ける社会を目指しています。
2023年度の採択課題である「高齢者の認知機能低下の早期発見におけるリモコン操作およびケーブルテレビ視聴傾向分析の有用性に関する検討」では、保健看護学部が研究代表となって、江東区高齢者医療センター、ケーブルテレビ会社などとともに、まずは認知症シニアの特性の解明に取り組んできました。
また、「ICTリタイリーズ(定年退職者)健康支援システムの開発および評価」や「高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるAging in Place推進に関する学際的研究」など、個人レベルでの加齢に伴う事象を明らかにするとともに、社会や地域における高齢化の課題について総合的に検証する研究を推進しています。

社会実装につなげる共同研究を展開する「COI 展開プロジェクト」
COI展開プロジェクトは、COI研究の研究成果を社会実装につなげることを目的として、立命館大学や企業と共同研究を行い、さらに一歩進んだ応用研究を展開しています。行動変容や社会参加(アクティブエイジング)を促すために、AIやIoTなどの最新テクノロジーを積極的に取り入れていることもプロジェクトの特徴です。
代表的な研究の一つである「スマートウェア技術搭載アイマスク型デバイスを用いたドライアイに対する個別化医療」では、ドライアイの原因となるマイボーム腺機能不全に有効なアイマスク型デバイスを開発。デモ機を用いた介入試験を進める一方で、2025年の社会実装を目指して企業との共同研究にも取り組んでいます。
また、「乳がん術後、在宅リハビリテーションの新たな試み」では、順天堂大学医学部附属静岡病院の外科医や作業療法士らが中心となって、乳がん手術にともなって腕の動きが制限されてしまった患者さんの腕の関節可動域を検出するスマートウェアを開発中です。これまではデモ機を使った臨床応用によりデータを蓄積し、リハビリ効果の評価などを進めてきました。現在は、本格的な製品化に向けて、ウェアの着心地やユーザーインターフェイスの改良を行っています。


退職後の健康維持に有効な予防的支援を探る
健康の維持・増進につながる“行動変容”を促すことは、本センターが重視する研究テーマのひとつです。運動が健康にとって大切だということは誰でも頭では理解していても、なかなか行動に移せない…。そのような心理的ハードルも加味して、スポーツ医科学、健康支援ICT、行動科学などの各方面から、「ICTリタイリーズ健康支援システムの開発および評価」という産学共同研究(ジェロントロジープロジェクト採択課題)に取り組んでいます。
スポーツ健康科学部の川田裕次郎准教授が研究代表を務めるこの研究課題では、定年退職前後の従業員(リタイリーズ)の健康に焦点を当て、退職後の行動変容につながる健康支援システムの開発を目指します。企業などに勤めている間は定期健診が義務づけられており、健康保険組合からの働きかけもありますが、定年退職後にはそのような健康支援が受けられなくなることを想定して、退職前から働きかける仕組みを開発しようというものです。
プロジェクト1年目となる2023年度は、3000人の定年退職前後者(リタイリーズ)へのオンライン調査を実施。定年退職前より後のメンタルヘルスが良好になっていること、特に運動実施・継続者においてその傾向が顕著であることなどを明らかにしました。
こうした調査結果などを踏まえて、沖電気工業とともに行動変容型介入アプリを開発。健康保険組合および全国健康保険協会支部の5団体を通じて募集したリタイリーズによる3カ月間の介入試験を行い、介入前・後・フォローアップ期で、習慣化がされたかどうかなどの質問調査でシステムを評価します。そして、本研究成果をまとめて、高齢者の健康支援に「プロスペクティブな予防措置」が重要であることを提案します。
地方からアジアへ、センターの知見を高齢モデル化

ジェロントロジープロジェクトでは、千葉県内の複数の自治体、高齢者施設などと連携した研究課題「フレイルの新規スクリーニングツールの開発とフレイル対策拠点の構築」が進行中です。順天堂大スポーツ健康科学部と保健看護学部などが中心となって行うこの研究課題は、千葉県の富里市や成田市の協力を得て、地域住民を対象に、COIプロジェクト(ロコモ予防運動プログラムの開発と社会実装)の研究成果に基づいたフレイル対策を実践します。
フレイル対策としては、フレイル予防基礎講座をはじめ、「カラダ改善プロジェクト」、「おうちで筋トレ☆動画配信」、「シニア健康カレッジ」といった企画に地域住民に参加してもらい、体力測定・評価まで実施。その結果を踏まえて、フレイル対策としての講義や運動指導の成果を評価する手法も明らかになりました。
ジェロントロジープロジェクトでは、千葉県のほか、三島キャンパスが中心となって静岡県伊豆の国市で行っている地域連携の研究課題が進行中です。いずれはそれぞれのキャンパスや学部、病院がコアとなってさらに広がり、全学体制で社会実装を推進することを目指しています。
さらにその先には、プロジェクトの成果を高齢化モデルとして、アジアの国々に展開することができるかもしれません。例えば、今はまだ若者が多いタイで、高齢化する前の今のうちに運動による予防的介入をするなど、高齢化先進国である日本の強みを活かした国際展開にも可能性を感じています。

研究者Profile

内藤 久士
Hisashi Naito
健康総合科学先端研究機構ジェロントロジー研究センター
センター長
【関連記事】アスリートのパフォーマンス向上から生活習慣病予防法の開発まで!国内外の研究をリードするスポーツ健康医科学研究所
【関連記事】子どもから高齢者、トップアスリートまで最先端科学を用いて スポーツと健康の関わりを探究
Researchmap