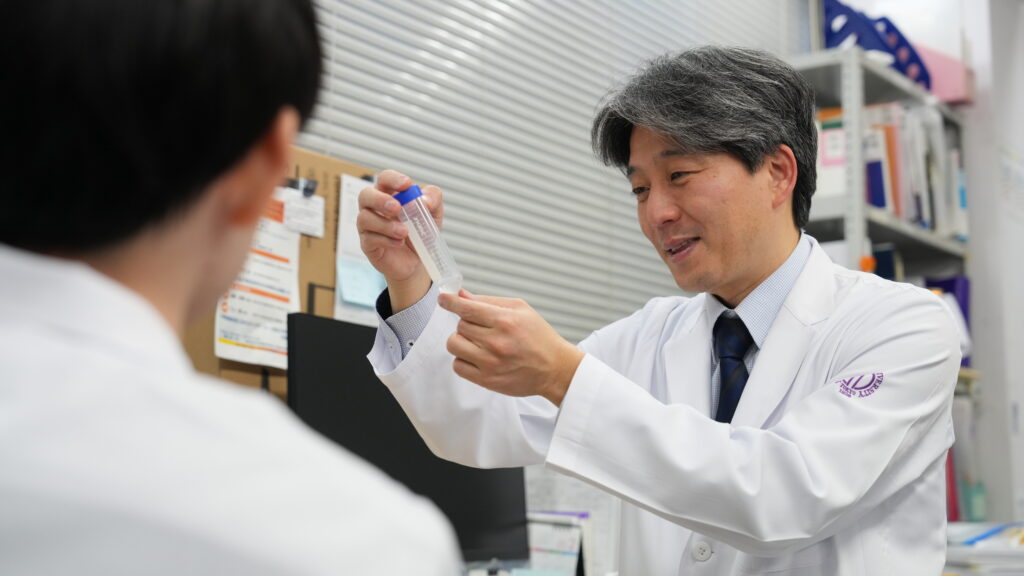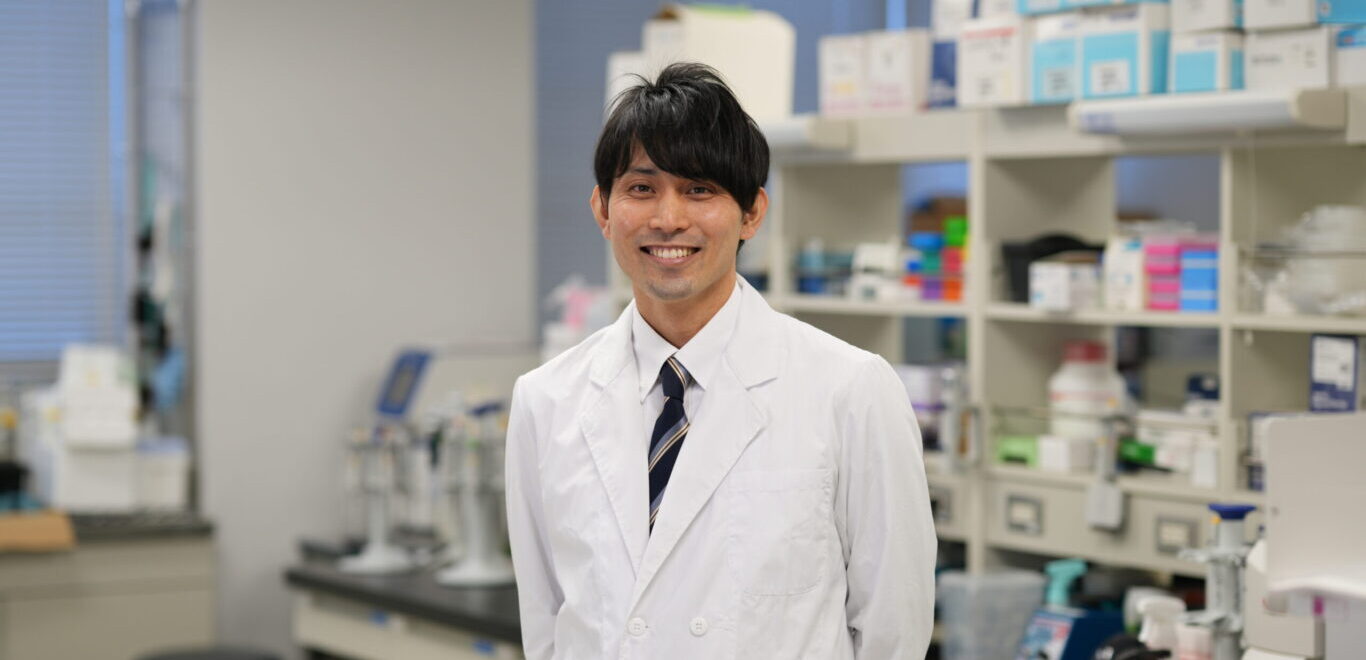
デスクワークなどの増加に伴い、座りっぱなしの生活時間が増えている現代人。いわゆる「運動不足」である慢性的な身体的不活動は、高血圧、喫煙、高血糖に次ぐ世界第4位(日本国内では第3位)の死亡を招く危険因子となり、公衆衛生の大きな課題になっています。スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科の吉原利典准教授は、その「運動不足」という国内でも数少ない研究分野を大きなテーマに掲げ、遺伝子発現の制御に関わる「エピジェネティクス」の観点から、運動不足がもたらす影響について、エビデンスの創出とメカニズムの解明に取り組んでいます。
環境因子で左右される遺伝子の発現

私の研究は私自身のスポーツ経験をきっかけにした、学部生時代の筋萎縮に関するテーマからスタートしました。運動生理学や生化学の分野で研究に打ち込み、その後、大学院を修了した頃から取り入れはじめたのが、「エピジェネティクス」と呼ばれる遺伝子発現に関する着眼点です。
エピジェネティクスとは、ギリシャ語の「epi」(=後で・上に)と、「genetics」(=遺伝学)を組み合わせた言葉で、DNAの配列を変えずに、細胞が遺伝子の働きを制御する仕組みのこと。たとえば一卵性双生児の場合、遺伝子の設計図は同じですが、食べるものや生活習慣など環境のさまざまな違いによって、体型や体力レベルなどが異なってきます。これは環境的な要因によって、DNAやDNAを取り巻く周辺構造に“付箋のような印”がつけられて、特定の遺伝子を活用するスイッチがオン/オフになるからです。すでに発がんや老化など、さまざまな疾病で関係性が明らかになっているエピジェネティクスによる遺伝子の発現調整の異常を運動不足に応用し、これまで骨格筋の萎縮に関連するエピジェネティクスの解明や、若年期の生活・運動習慣が加齢性疾患の原因になるかを研究してきました。
軸として取り組んできたテーマのひとつに「マッスルメモリー」が挙げられます。これは、運動によって骨格筋における遺伝子の“付箋のような印”に起きる変容を明らかにするもの。この研究を通して、若年期に運動をしていると染色体を構成するタンパク質のひとつであるヒストンの長期的なアセチル化が生じ、ブランクがあっても再び運動をした時に適応が早く、サルコペニア(加齢や疾病による骨格筋の萎縮)の抑制をはじめとした、中年期以降の健康問題の対抗手段になり得ることが明らかになりました。

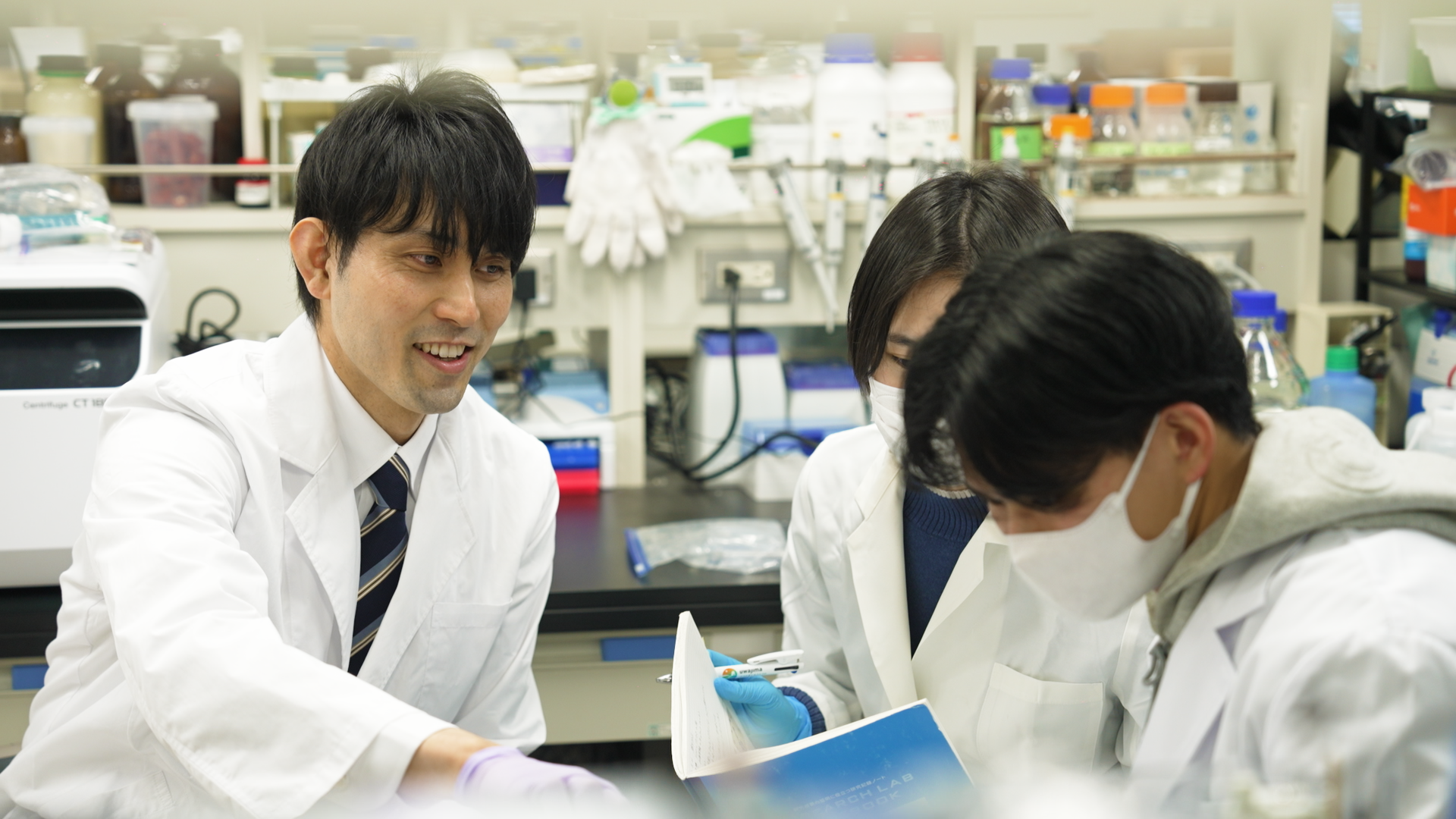
革新的な研究テーマでさらなる高みを目指す
順天堂大学で特任助教を務めていた2014年以来、2021年に採択されたテーマに至るまで、研究代表を務める4つの研究で継続的に科研費に採択されてきました。そして2023年、創発的研究支援事業に新たに採択されたのが、現在注力する「運動不足が世代を超えて伝播する分子メカニズムの解明」という研究です。前述した研究テーマをはじめとして、これまでの運動不足とエピジェネティクスに関する研究は、あくまで一個体、一世代での遺伝子の発現調節の異常を対象としたものです。そこからの発展とともに、今回は創発的研究としてより挑戦的で、社会にイノベーションをもたらすテーマを策定。「運動不足」による遺伝子の発現調節の異常は次の世代に引き継がれるのか、という切り口で仮説を立てました。
親が子どもに与える影響について、近年では胎生期・発達期に母親が曝される環境要因が、子どもの生活習慣病に起因する死亡リスクや健康寿命を左右する重要な因子だと考えられています。また慢性代謝疾患(糖尿病など)を罹患する父親の場合、早産や低出生体重児のリスクが高いことも明らかになっており、発達期だけでなく、妊娠前の父親の生活習慣が子どもに与える影響も示唆されています。過去の研究では、胎児期の母親の低栄養・過栄養、がん、化学物質、ストレスなどの環境要因がDNAのメチル化を介して、エピジェネティクスの影響を子どもに与えることが明らかになった一方で、母親の「運動不足」が与える影響の可能性については、科学的なエビデンスやそのメカニズムが不足している状況。その分子メカニズムを明らかにするエビデンスの創出が、この研究テーマの大きな狙いです。
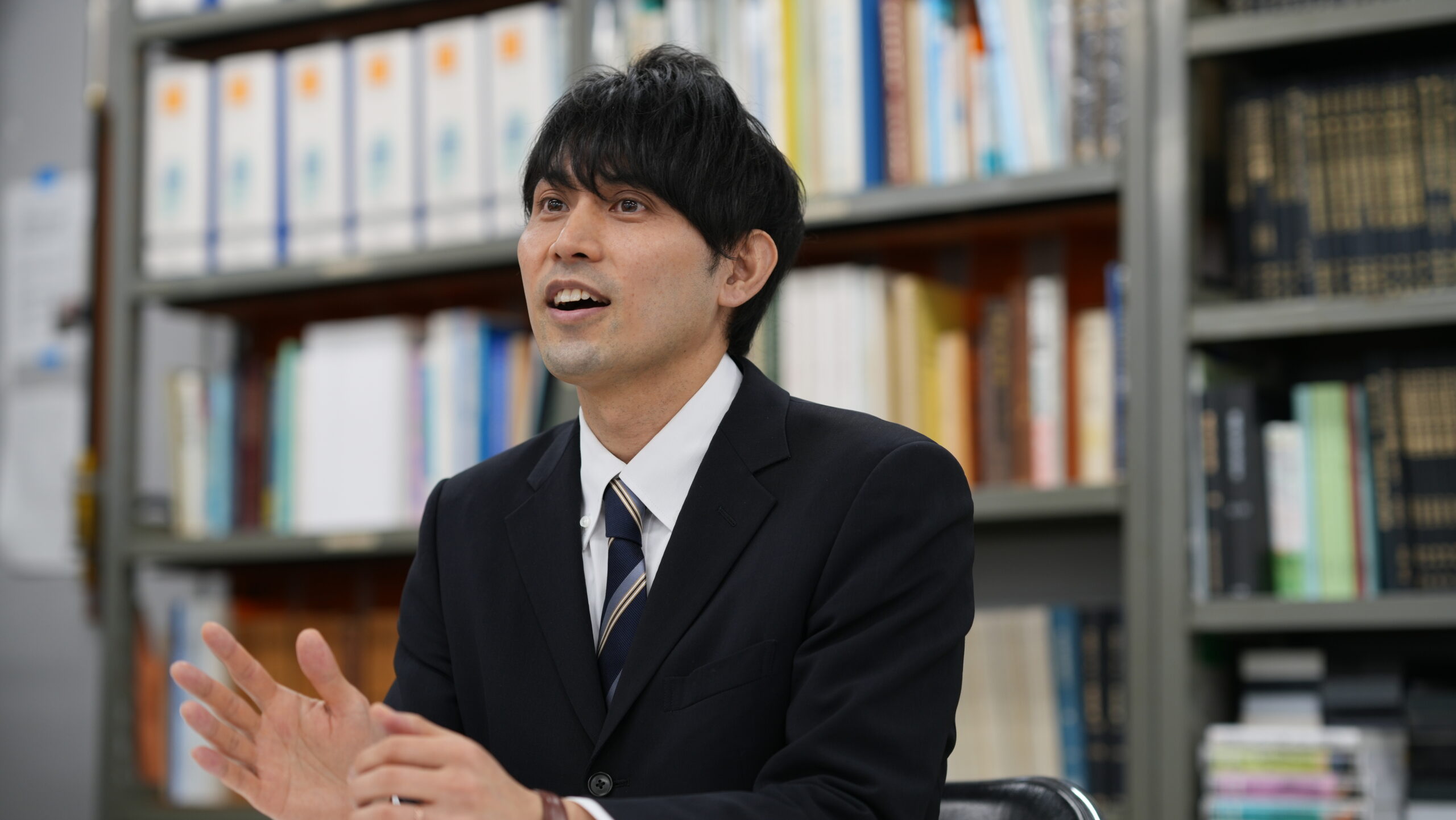
運動不足による健康リスクは世代を超えるか
2029年までの創発的研究支援事業として2段階の研究フェーズを想定しています。第1フェーズはこれまでの研究成果を引き継ぎ、一個体として運動不足によるDNAのメチル化の発生とそのメカニズムを明らかにするもの。独自に作成した活動制限モデルで8週間の運動不足状態に置いた雄性・雌性のラットのヒラメ筋サンプルを対象に、RNAシーケンスによる発現変動遺伝子を解析。すでに雄性・雌性それぞれと、雄・雌で重複する発現変動遺伝子の存在を確認しており、独自に確立した特定のゲノム領域のDNAメチル化状態の検出手法を用いたエピジェネティクス遺伝子の特定や、遺伝子の発現を制御する遺伝子プロモーター領域のDNAメチル化の解析を進めています。この後、第2フェーズでは次世代への遺伝を調査するため、生殖細胞の機能評価や第2世代の個体の遺伝子解析を進めていく計画です。
この研究の大きなポイントは、運動不足が自分だけでなく、子どもや孫に至る将来的な健康リスクにつながる可能性を明らかにすることです。現代では生活習慣病の予防は中高齢者を対象とすることが多いですが、もっと視点を前倒しして、若年期から、もしくはその親の世代からと、より早期の運動不足対策の必要性が明らかになるかもしれません。その影響は生活習慣の改善を社会に訴えかけることに付随し、医療費の大幅削減や教育システムの改革などにも波及するでしょう。また多因性疾患に対する医学的な新たなアプローチ、薬理学的な運動効果模倣薬の開発といったインパクトも計り知れません。運動不足に対する「世代を超えた生涯にわたる健康対策」が必要であるというエビデンスの創出は、社会に大きなイノベーションをもたらすものとなるはずです。


30代で見出した研究者人生をかけるライフワーク
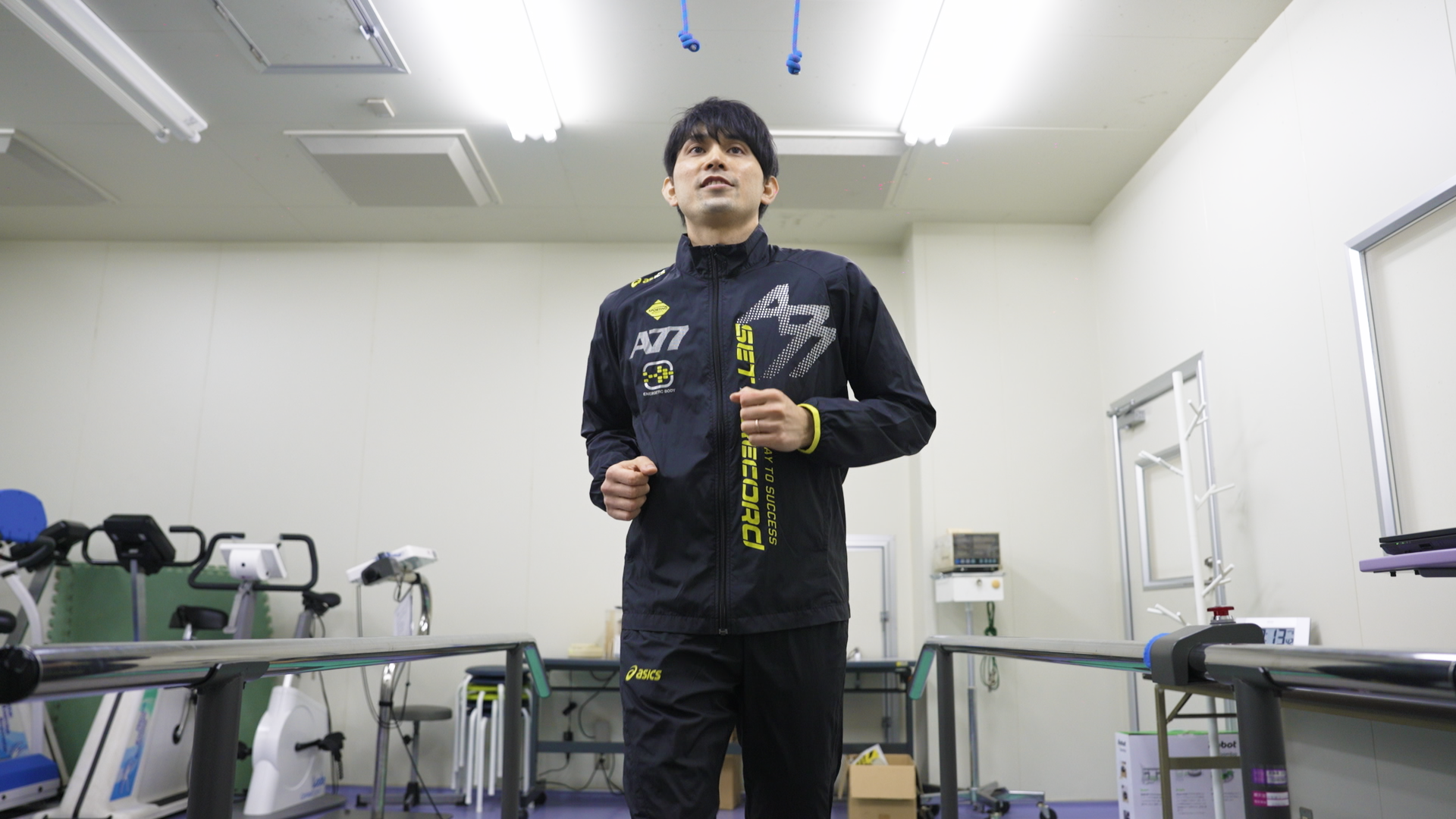
この研究テーマに至るまで、最新医療の研究はもちろん、スポーツ遺伝学においても世界最高峰のレベルにある順天堂大学の環境が大きな刺激になりました。もともと運動生理学や生化学を起点とする私が遺伝子学について知見を深められたことも、順天堂が擁する研究環境やスポーツ遺伝子学のトップランナーをはじめとした、他の研究者とのつながりを抜きには語れません。
「運動不足が世代を超えて伝播する分子メカニズムの解明」というテーマは、おそらくこれからの私の研究者人生における、大きなライフワークとなるでしょう。細分化した研究テーマは途方もなく広がりますし、一方で数だけでなく、より質の高い論文の執筆も意識しています。また、現時点でも昭和大学 臨床薬理研究所の秋山雅博准教授と「運動不足と腸内細菌」の融合による新たな領域での研究を進めるなど、学内外を問わずさまざまな研究機関や企業などとのつながりも見据えています。2022年からは単独での研究室の運営もスタートし、ともに研究に取り組む後継の育成にも注力しています。ぜひともこのテーマに賛同していただける、関心をもってもらえる研究者の方々、研究者を目指す方々がいらっしゃるようでしたら、ともに大きなイノベーションを目指して協働したいと考えています。
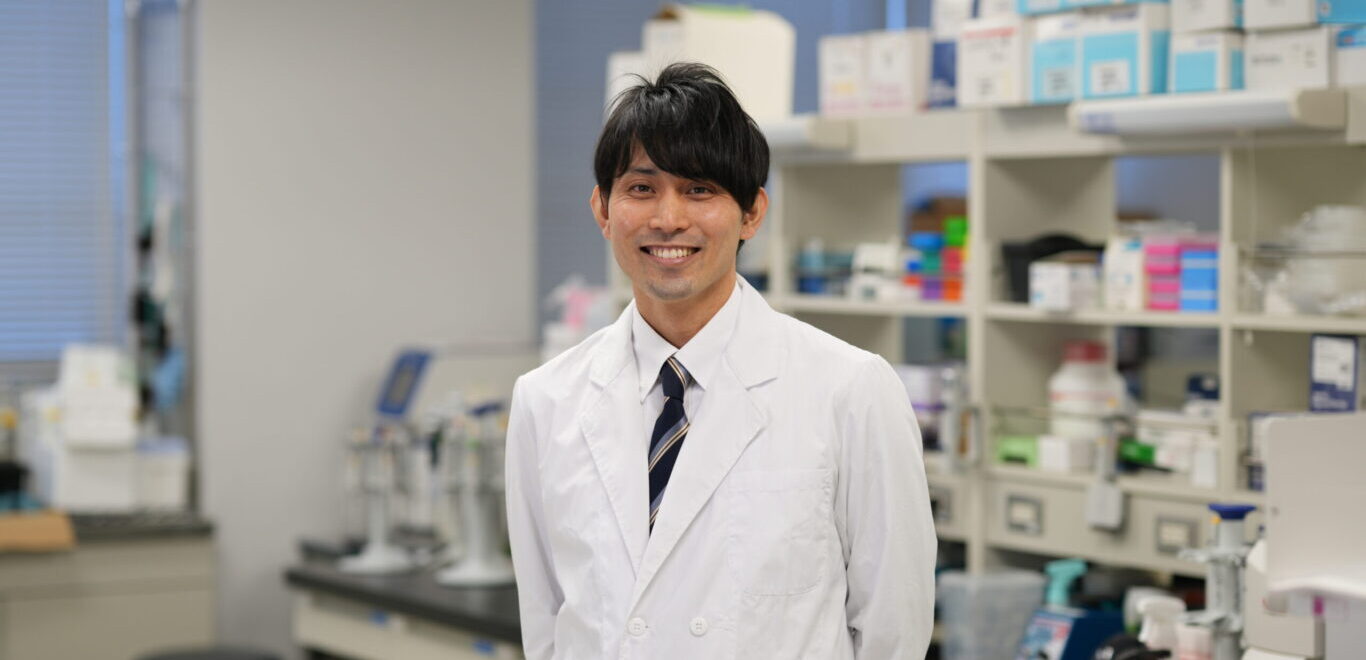
研究者Profile
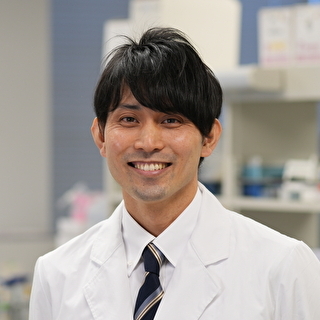
吉原 利典
Toshinori Yoshihara
スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科/大学院スポーツ健康科学研究科
准教授
【関連記事】アスリートのパフォーマンス向上から生活習慣病予防法の開発まで!国内外の研究をリードするスポーツ健康医科学研究所
【関連記事】子どもから高齢者、トップアスリートまで最先端科学を用いて スポーツと健康の関わりを探究
Researchmap