学生生活・キャリア Juntendo Scope
- スポーツ健康科学部
- スポーツ健康科学研究科
- 在学生
2年前、あの座談会で語った夢と今—研究と向き合った日々の先に ~運動開始のタイミングと心周期の関係性について~
博士前期課程2年
金箱ちひろ さん

2年前に開催された2つのテーマの座談会「スポ健で見つけた私の学び 卒業研究を振り返る」と「学部生から修士課程に向けて&私たちがスポ健を選んだ理由」では、学部時代に取り組んだ卒業研究を振り返りながら、修士課程への期待や不安、そして自身の学びをどのように深めていきたいかを5名の学生が語ってくれました。
彼らが修士課程の2年間でどのような研究に取り組み、どのような成長を遂げたのかを、一人ひとりのストーリーとしてお届けします。
第1回は、生理学研究室で研究を行った金箱ちひろさんの歩みを紹介します。学部時代には、高校まで取り組んでいた陸上競技の経験を活かし、「外的および内的なタイミングでの運動開始と心周期の関係」を研究しました。
修士課程では、「運動開始のタイミングと心周期の関係性についての研究」のタイトルで修士論文をまとめました。主に、運動開始のタイミングがパフォーマンスに与える影響に焦点を当て、スタート動作がパフォーマンス向上にどのようにつながるのか、その要因を探る研究に取り組みました。
―修士課程で取り組んだ研究について教えてください
スポーツにおけるスタートパフォーマンスの向上に生理学的な視点からアプローチしたいと考え、運動時に欠かせない自律神経活動の一つである心臓の活動に着目をして、主にスタートパフォーマンスとの関係性を探るための研究に取り組みました。
―修士論文について教えてください
修士研究のタイトルは「運動開始のタイミングと心周期の関係性についての研究」です。
この研究では、運動を開始するタイミングが心周期のどの位相(収縮期または拡張期)にあるかによって、運動パフォーマンスが変わるのかを検討しました。実験ではヒトを対象に、様々な条件で跳躍課題を行ってもらい、記録した心電図データとパフォーマンス(跳躍高や反応時間)との関係を分析しました。
―研究を進めるうえでどのようなスキルが必要でしたか
研究を進めるためには、自身の研究分野に関わる生理学の基礎知識に加え、信頼性が高く、自身の修士論文と関連する最適な論文を探し出す能力が必要で、英論文を読み解く力が必要でした。ほかにも、実験の立案から論文をまとめるまでの計画性も重要であり、さらに、実験データを解析するために必要な統計学的知識、ExcelやWordの活用と応用スキルも必要でした。必要な情報を効率的に収集し、論理的に整理する力が鍛えられたと思います。このスキルは、今後のキャリアにも役立つと感じています。
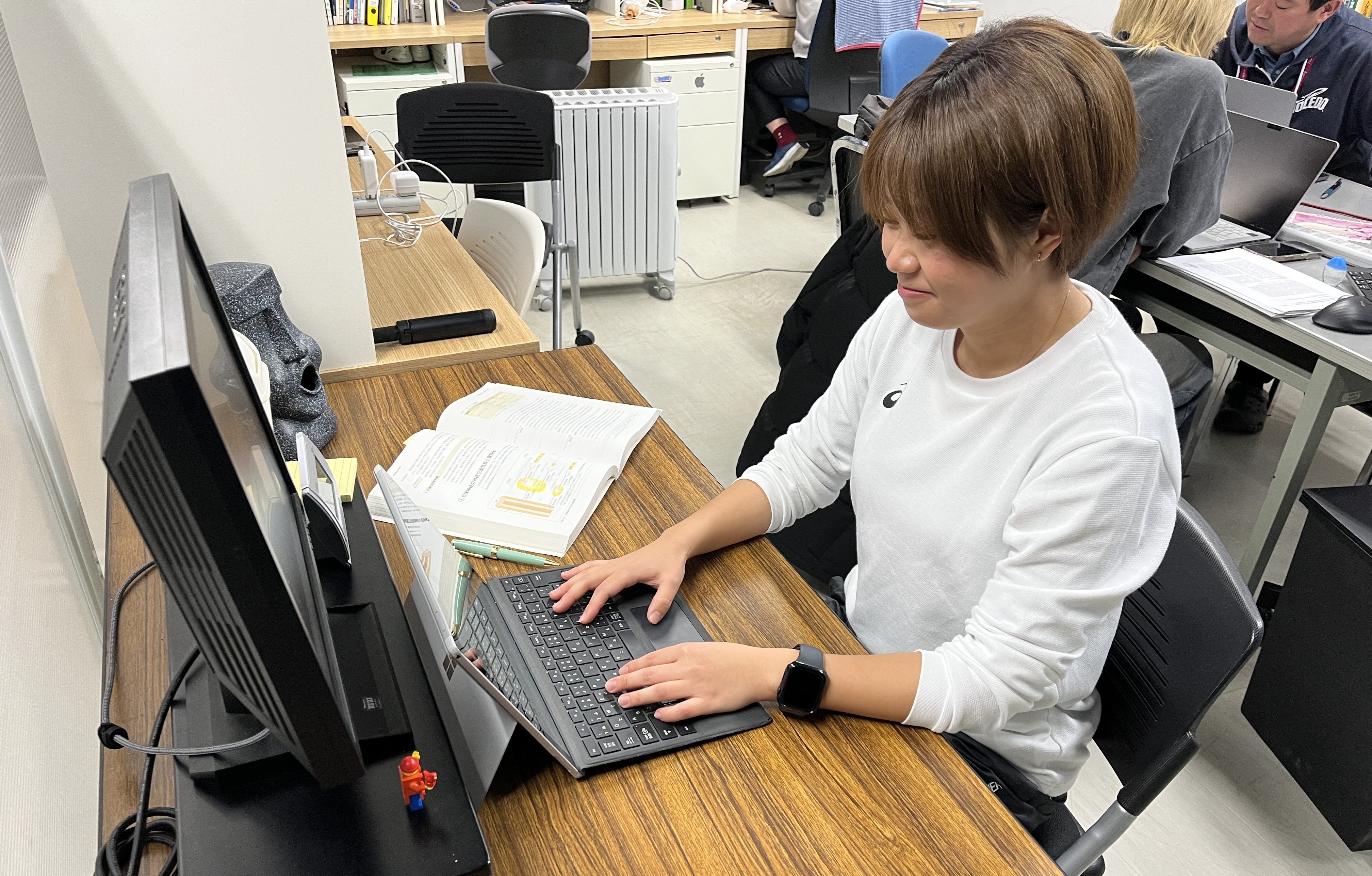
実験データを解析する金箱さん
―研究で用いた手法や工夫した点などがあれば教えてください
実験では、成人男女を対象にして様々な条件の跳躍運動の課題(例:Ready…Go!の音に合わせて素早く高くジャンプをする課題)を行ってもらいましたが、その際に記録した心電図や呼吸、床反力などのデータはデータ解析ソフトMATLAB(数値解析ソフトウェア)を用いて分析を行いました。
心電図波形にノイズが入りやすかったため、電極コードの位置や実験参加者の服装などを調整したり、リアルタイムモニターの波形を定期的に確認する作業を並行し、できる限り正確なデータがとれるように対処を工夫しました。また、参加者の集中力を保つような声かけをすることを心がけて実験をすすめました。
―修士課程での時間の使い方で工夫したことや、研究をおこなううえで苦労したことがあれば教えてください
工夫した点は、自身の研究分野に役立ちそうな情報を日常的に自ら取りに行ったり、体系的な学習を通して、自身の研究分野の理解を深めるようにしていました。
一方で、実験に関することで苦労したことがあります。特に、参加者の募集をして研究に必要な人数を集めることや、実験実施とデータの取得は苦労することが多くありました。実際に実験に取り掛かってみると、想定していたように計画的に進めることができないこともありました。12月上旬の修士論文の提出期限が迫るなか、特に後半は常に時間に追われながら修士論文の執筆に取り組みました。
―2年前の「キーワード」はどのように生かされたでしょうか?
2年前の座談会で掲げたキーワードは「なるようになる」でした。この言葉のおかげで、不安なときも考え込みすぎず、柔軟な姿勢で研究に向き合うことができました。
この言葉には、諦めのようなネガティブな意味と、「自分ができることはやり切った」というポジティブな意味の両方があります。私は特に後者の意味でこの言葉を使うことが多く、想定外の展開にも前向きに取り組めることが、自分の強みになりました。
―修士課程を通じて得られたことと、今後どのように活かすことができるでるでしょうか
私は研究を通じて、課題解決能力や論理的思考力、広い視野を持つこと、文章力など、多くのスキルを培いました。
修士課程修了後はスポーツ施設の運営を行う企業に就職する予定です。よりよい施設づくり目指すうえで、様々な面からアプローチできる考え方や力を備えたことは、今後のキャリアに大きく活かすことができると考えています。修士課程で得た経験を活かしながら、より良いスポーツ環境を提供できるよう努めていきたいです。
―これから修士課程を目指す方へのメッセージをお願いします
大学院は、多くの人に支えられながら、自分自身の力を大きく伸ばすことができる場です。決してブレない気持ちや目標を持っている人にとっては、かけがえのない貴重な2年間になると思います。
大学生までの生活とは全く異なる大学院という新しい世界へに飛び込むことになるかもしれませんが、覚悟を持って一歩踏み出す皆さんのことを心より応援しています。
結びに
この2年間、金箱さんは自身の研究テーマを深め、多くの困難を乗り越えて成長しました。学部時代に興味を持ったテーマから、よりパフォーマンス向上の視点へと研究を進め、多角的なアプローチを身につけたことが大きな収穫だったといえます。
次回は、精神保健学研究室で研究を行った近藤ちひろさんのストーリーを紹介します。

修了式後の謝恩会の様子 近藤ちひろさんと金箱ちひろさん
関連リンク