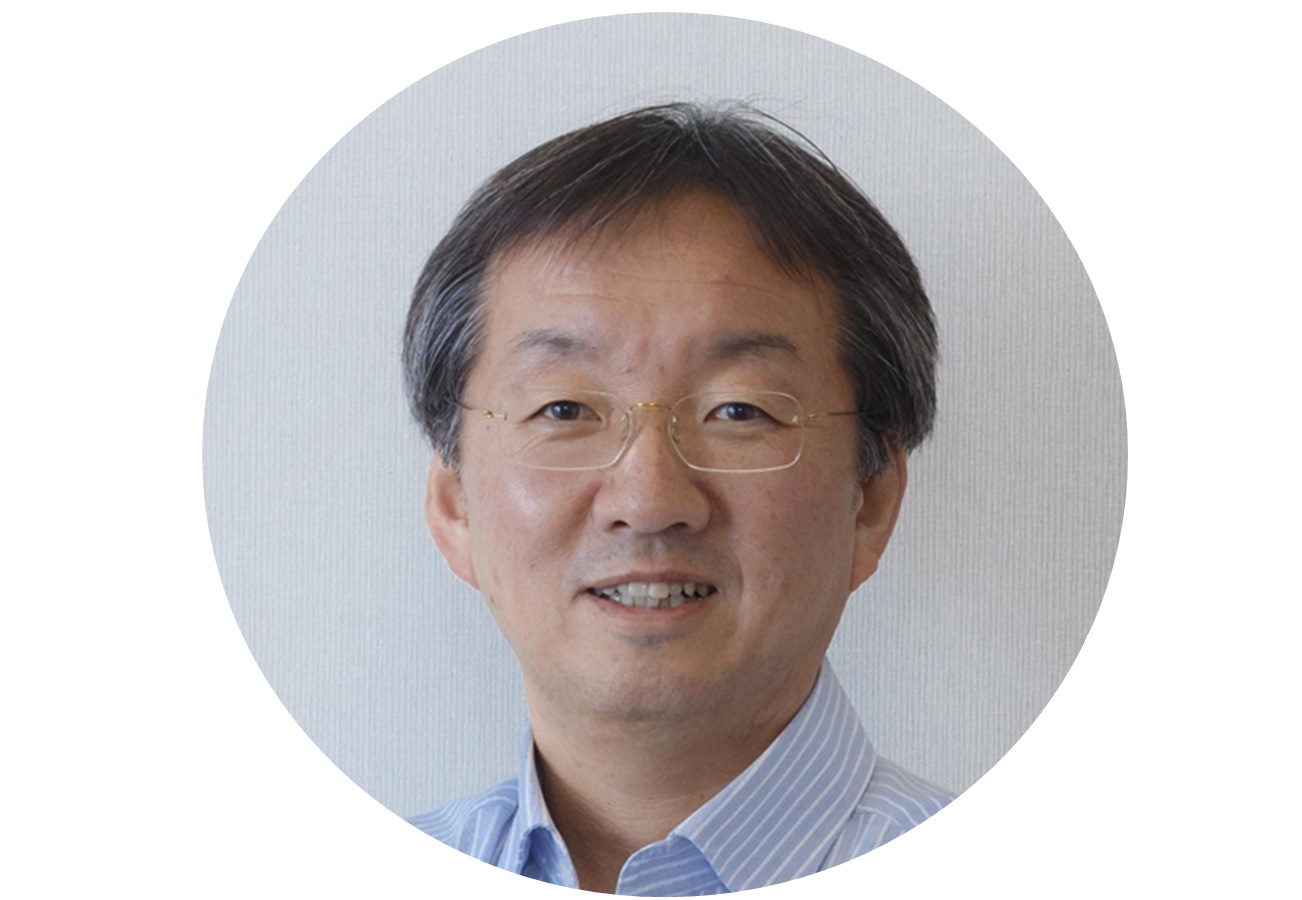研究科紹介 理学療法学専攻
理学療法学専攻について
国民の健康水準は、生活の質向上、医療技術の進歩、公衆衛生の進展等により向上していますが、急速な高齢社会の進展、経済の発展やグローバル化等による社会構造の高度化に伴い、人々の生活習慣や生活環境が変化して疾病構造も様変わりし、医療に対する期待や要望も多様化してきています。このような社会情勢のなかでリハビリテーション医療技術を支える理学療法士には、より高度な専門性と実践能力が求められるようになりました。本専攻では、医療機関や施設から地域に至る様々な場所において、それぞれの場の特性を理解し、個々人毎に異なる多様なニーズに対応し、個人の価値観や意思を尊重した理学療法を実践できる人材を養成します。
領域紹介
神経・運動制御理学療法学領域
超高齢社会とともに、理学療法の対象疾患である脳血管疾患・神経変性疾患・認知症などの中枢神経系疾患の有病率が増大しています。介護が必要となった主な原因は、すべての要介護度で脳血管疾患と認知症が要因の第1位と第2位を占めています。中枢神経系疾患に対する、効果的でエビデンスの高い理学療法の確立は喫緊の課題です。本領域では、この重大な課題に対して、神経科学の知識を理学療法学に応用し実践できる能力や、より高度な専門的実践能力を身につけることを目指します。
ヒトの動作は外部からの感覚情報をもとに脳内の知覚・認知過程を得て、運動の制御を行っています。近年の脳機能イメージング技術などによって脳機能の解明が進み、ヒトの運動制御の機構が以前の神経生理学的な知見よりも精密かつ詳細に明らかになっています。これらの運動制御はロボットの制御機構にも応用され、ヒトの運動制御の解明がロボット技術にも応用されています。機能低下の回復過程や、代償的な動作の効率化などの運動制御に対してアプローチする理学療法士としては、運動制御を熟知することは必須です。さらに、センサー技術の発展により、簡易的にヒトの生体情報を視覚的に取得でき、バイオメカニクスの観点からも解析が可能となりました。それらの技術を駆使した運動制御機構の解明とリハビリテーションへの応用は今後の理学療法分野に必須であり、運動機能制御について、より高度な専門的実践能力を身につけることを目標とします。
担当教員
藤原俊之、松田雅弘、藤野雄次、春山幸志郎、髙橋容子
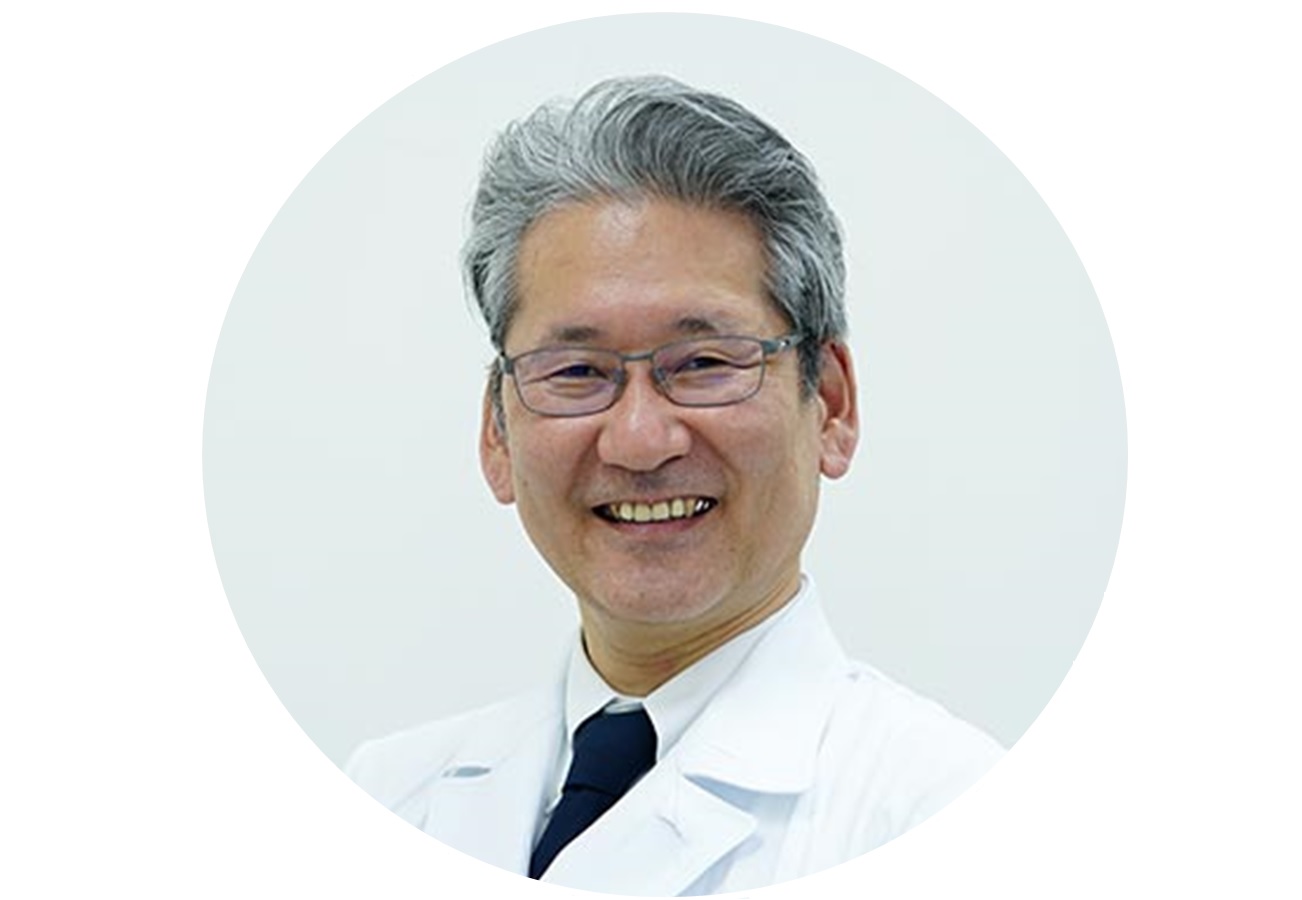
藤原 俊之 MD, Ph.D.
研究分野:リハビリテーション医学
研究キーワード:非侵襲的脳刺激、脊髄刺激による神経可塑性を誘導するリハビリテーション医療の開発、機能回復の神経生理学的機序

春山 幸志郎 PT, Ph.D.
研究分野:神経理学療法学
研究キーワード:神経筋疾患のリハビリテーション、小脳症候の機能評価、運動学習、歩行のバイオメカニクス、神経生理学

運動器・スポーツ理学療法学領域
本邦では運動器の健康づくりを通した活力ある社会の実現にむけた複数の政策が採用され、理学療法士が活躍すべき範囲は拡大傾向にあります。スポーツ庁「スポーツ基本計画」では、多様な主体によるスポーツ参画の促進が盛り込まれ、競技大会に限らず、日常的なスポーツ場面での健康増進や安全・安心確保において理学療法士が恒常的に寄与することが期待されています。一方、近年の高齢化および生活習慣の変化や、多種多様なスポーツ浸透に伴い、日常生活、職業、スポーツでの身体活動による障害・外傷が増えています。これらの身体活動をより健康で安全・安心に実施継続するために急性期対応、周術期管理、活動復帰支援における医学的知識・身体機能的知識を持つ理学療法士への期待が高まっています。運動器の健康や様々な活動参加をベースとした健康寿命の伸延と、生産性の維持・向上が大きな社会課題となることから、この分野でのより高度な専門的実践能力を養うことを目標とします。
担当教員
池田浩、相澤純也、飛山義憲、宮森隆行、澤龍一、姉帯飛高
内部機能障害理学療法学領域
社会医療診療行為別統計(平成30年6月審査分)によると、疾患別リハビリテーション料は脳血管疾患等リハビリテーション料が約40%、運動器リハビリテーション料が約47%、廃用症候群リハビリテーション料が約8%とあわせて約95%を占め、呼吸器リハビリテーション料(3%)、心大血管疾患リハビリテーション料(2%)と極めて少ない状況です。一方、傷病分類別の入院患者は、2015年以降、呼吸器系の疾患、循環器系の疾患、腎尿路生殖系の疾患といったいわゆる内部機能障害のもととなる疾患が脳血管疾患や運動器疾患に比べて大幅に増加することが予想されています。特に日本のような超高齢社会では単一疾患でなく、多疾患による重複障害者が増えていることに加えて、心不全患者や透析患者など「安静が治療」であった対象でも運動療法が身体機能を改善し寿命を延ばす治療である科学的エビデンスが増加し、理学療法の対象者は多様化・複雑化していることから、内部機能障害についてより高度な専門的実践能力を持った理学療法士の養成を目標とします。
担当教員
高橋哲也、齊藤正和、石川愛子、岩津弘太郎

急性期高度専門理学療法学領域
順天堂大学大学院保健医療学研究科では、2025年度より新たに
担当教員
藤原俊之、高橋哲也、齊藤正和、飛山義憲、藤野雄次、岩津弘太郎